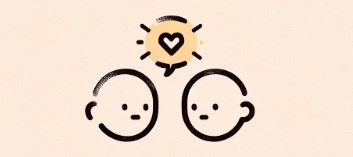復習を身に付けさせるために必要なステップとは?

中学受験を目指す子は、自身での復習ノートを使って復習することが必須と言います。
これまで実施した問題で間違えたところや苦手なところを自身でピックアップして自己学習できれば言うことないと思いますが、年次やその子の自立状況を踏まえて段階的に進めないととうまく行かない部分でもあると思います。
復習というのは細かく分解すると以下の作業に分かれています。うちではそれぞれの作業を段階的に子ども自身が自立的にできるように支援しながら進めています。
| 復習のサイクル | 自立してやるための課題 |
| 1.演習を実施する | 自発的に取り組めない(学習習慣がついてない) |
| 2.答え合わせを行い、間違った問題を認識する | マル付けがテキトーで間違った問題をマルにしてしまう |
| 3.解答・解説を確認して解き方を理解する | 解説を読んでも理解が追い付かない |
| 4.理解した解き方を自身の言葉でノートに記述する | 記述した内容が意に即していない場合、指摘が必要 |
| 5.数日後、間違えた問題に再トライする | 1と同様 |
| 6.答え合わせを行う | 2と同様 |
Step1:学習習慣をつける [項番1,5]
あたりまえですが復習を始める前にまず演習を自立的に取り組めるようになっておく必要があります。塾などで強制的にやってもらうことはできますが塾でも復習後の演習2周目は各自に任せることが多いので、子ども自身で演習に取り掛かる習慣ができている必要があります。
うちでは演習1周目(項番1)は塾で実施し、演習2周目(項番5)は家庭でやっています。
Step2:答え合わせをさせる [項番2,6]
復習を自立的にやってもらう第2ステップは答え合わせを子ども自身でできるようになってもらうことです。この作業を親が実施するのは負担が大きいため、ここから手をつけます。
ただ答え合わせなんて解答冊子を見ながらマル付けするだけ、と思いきや実際にやってもらうと不正解をマルにしてしまっていることがあります。このマル付けが間違うと復習のサイクルが回らないので誤りなくマル付けができるようになるまでは親の再チェックが必要です。
うちでは子どもがマル付けしたものを親が再チェックしている状態です。
Step3:解き方と何が違ったのかを理解する [項番3]
間違った設問が明らかになったら、その設問の解き方を解答冊子を読んで、どこが違ったのかを子どもなりに腹落ちしてもらいます。
塾の授業では解き方を説明してくれる設問と、そうでない設問があるため、この作業は家庭学習の中でやる必要があります。子どもひとりだと解説を読んでもわからないことがあるので親と一緒にやっています。
ある程度、思考のベースができたら「なぜこの設問はこの解き方だとダメなんだろう」を塾の先生に質問できるようになっていくと思いますが、現在、うちでは家庭学習の中で9割を解決し、残り1割を塾の先生に質問するという割合でやっています。
Step4:解き方を自分の言葉でノートに書く [項番4]
間違った設問に対して何が違ったのか、正しい解き方はどうなのかが理解できたら、それを子ども自身の言葉で復習ノートに書いてもらいます。
ノートに書いてもらうのは手書きによる記述により記憶への定着を図ることもありますが、また同じような設問で誤ったときに振り返りできるようにすることの方が主目的だと考えています。この復習ノートを使って「前回は解き方をどう間違えたんだっけ?」を思い出すサイクルになったら、復習サイクルは完成と思ってます。
うちでは新小4からこの作業を始めてます。現時点は家庭学習の中で親と一緒にやっています。
まとめ:小学4年生で復習サイクルの自立化を目指す
以上のステップを経て、晴れて復習サイクルの自立化に到達するという考えのもと、これを小学4年生のゴール目標とし目下訓練しているところです。
これができるようになると、子ども自身で演習を実施し間違った設問の解答で理解が追い付かなかったところだけを親に聞いてもらうというサイクルで自主学習が進みます。そうなると学習効率が飛躍的に向上すると思います。またその状態であれば塾の先生にも聞ける状態になっているため、塾の自習室での学習も効率的にできるようになっているということでもあります。
この状態に到達したとしても親としては定期的に演習の結果を見て、復習サイクルが回っているか、前回間違ったところの正答率が上がっているかを定期チェックする必要があると考えてますが、今年はこの状態になることを目指して親子ともども訓練していきたいと思います。