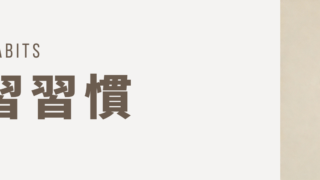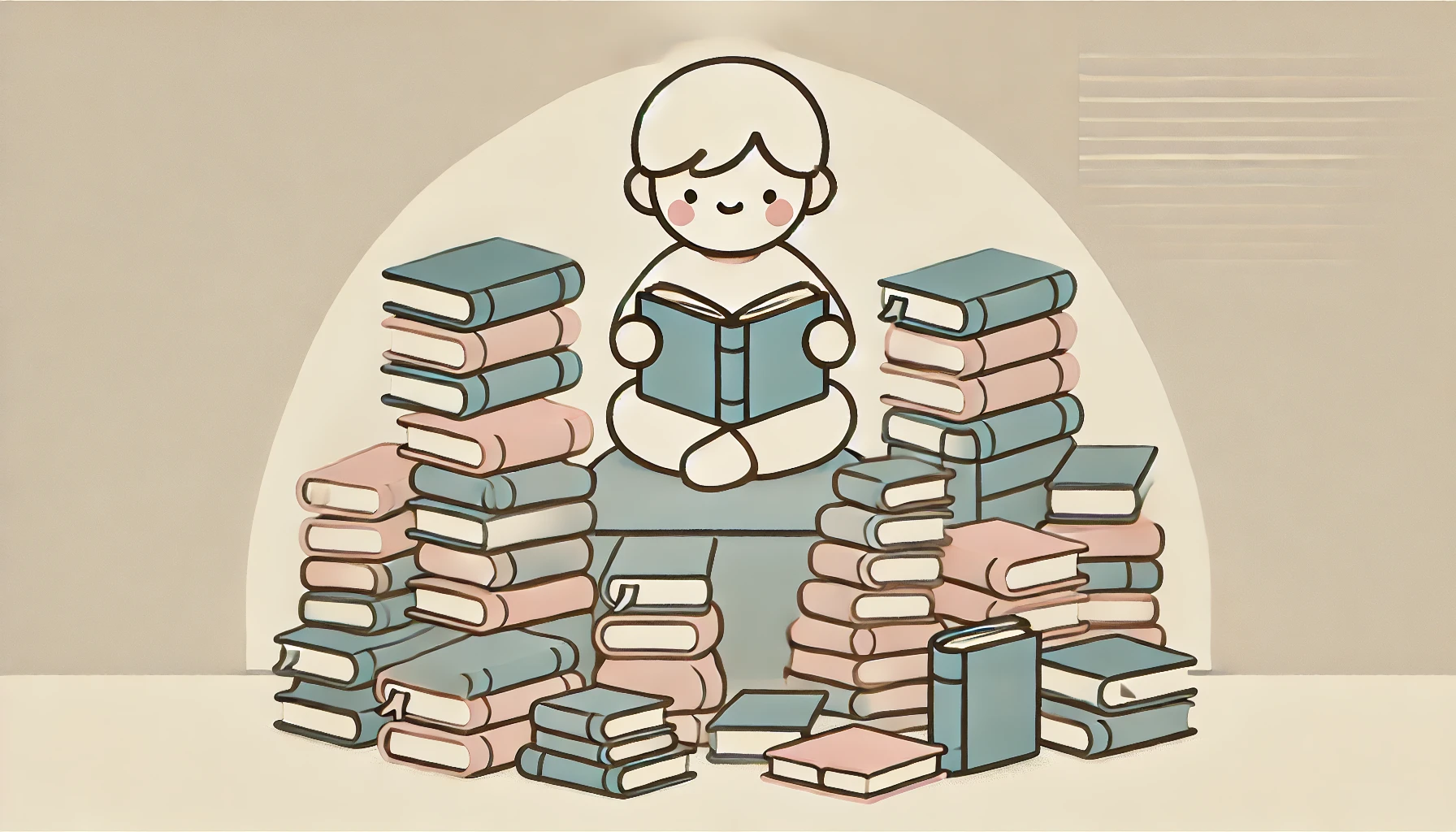防災イベントで防災意識と社会の仕組み(自治体)を学ぶ

うちでは中学受験に向けて日々学習をしていますが、いまの時期は勉強だけでなく外に出て色々な体験をさせてください。とアドバイスをいただくことも多くあります。
その意図は「子どもの気分転換」と「適性検査(作文)での引き出しを増やす」です。
うちでは、色々な体験のひとつとして「防災イベント」に参加してます。今回はその内容についてご紹介します。
防災イベントとは?
たまに公園や小学校でやっているのを見かける気がするけど、具体的に何をしているのか、あまりピンとこないという方、多いと思います。私もそうでした。
良く見かけるのは公園でやっているものです。こちらは主に展示体験中心のイベントです。消防車に乗れる、消防隊の服が着れる、消防車での放水を体験できる、といったものです。
うちでは、このイベントも参加することがあるのですが、今回取り上げるのは小学校でやっているイベントです。このイベントの実施要領は主に以下のパターンが多いです。
- 小学校の配布物等で開催の案内がある(年1、2回)
- 基本的に事前応募制、定員割れしている場合は当日の参加もOK
- 休日の午前中(2~3時間)を使って開催、基本応募者はフルタイムでの参加
自治体の方々と自衛消防団や消防署の方々が運営されています。
イベントの内容は?
小学校でやっている防災イベントの内容は以下のようなものです(地区によって若干の差異があるかもしれません)
- 地震発生のメカニズム等の災害に関する基礎情報の学習(講義やビデオ鑑賞)
- 災害レベルとハザードマップの見方、それを踏まえた周辺河川の危険度解説
- 仮設ベッドの寝心地体験、非常用持ち出し袋の重さ体験
- 火を使わない非常食の作り方のレクチャ
上記の内容を2~3時間かけて自治体の方々がしっかりと教えてくれます。途中抜けは基本なしで半分勉強、半分遊びといった雰囲気での体験になります。実践的な内容が含まれているので大人もタメになる内容になっています。
まとめ:防災イベントで自治体を知ることができる
小学校の社会の授業では地図の見方や自治体等の学習から始めることが多いと思いますが、自治体のように教科書だけではイメージが湧きにくい領域もあると思います。ただ小学校の授業だけだと時間割の関係でサラッと解説して終わりということもよくあります。
「防災イベント」は自治体(自営消防団、消防署)の方々とのふれあいを通じて、身近にあるのに意識しないと理解しにくい自治体を理解する助けになると思います。
もちろん防災イベント本来の目的である「災害時にやること(やってはいけないこと)を知る」「ハザードマップを見て災害時のことを事前に考えておく」も、しっかりと体験できます。
こういった地域で住民の生活を支えるための社会の仕組みや、災害時に考えておかないとならないこと等、実社会とつながっていることをダイレクトに理解しておくことで、作文力の根幹にある自分の考え(引き出し)を持つことができると思います。
まだ参加したことのない方は一度参加の検討をしてみてはいかがでしょうか。