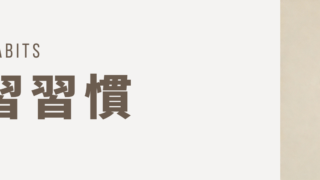子ども自身でタイムスケジュールを立てて実行することで段取り力が向上する

算数を制すものは中学受験を制すと言われるように算数力の向上は重要です。
四則演算を正確かつ早くこなす計算力や図形問題を解くための空間把握力は基礎体力として必須なチカラですが、それだけでは応用問題を突破することはできません。
応用問題を解くために必要なチカラのひとつとして条件を整理して段取りを考えるチカラがあると言われます。SAPIXに通う子はこのチカラが高いと言います。
うちでは、このチカラを養うための方法(習慣)として家族で出かけるときは、その日のタイムスケジュールを子どもに書いてもらうようにしています。
具体的には以下のようなことを実施しています。
- 家族で出かける日の行動予定をあらかじめ書いてもらう。何時に起きて、何時に出発して、何時にどこを通過して、何時に到着するかを分単位で計画立ててもらう(宿泊を伴う場合は食事・入浴・宿題の時刻まで記載)
- 当日は出来る限り、そのスケジュールに沿って行動をする。
タイムスケジュールを作る時は、GoogleMap等の地図アプリを使い、目的地に何時頃に到着するかを確認し、その分単位の予定を書いてもらいます。あまりに無理な予定だなと感じた時はその場で「もし混んでたらもう少しかかるんじゃない」とか「この短時間でご飯食べれるかな」と伝え、子どもに納得してもらったうえで予定を修正してもらいます。
そして当日はスケジュールに沿って行動します。時間どおりにいかないこともありますが、できるだけ時間に沿って行動します。例えば予定より実際の行動が予定より遅れていたら急ぐようにします。
うちではこれをお出かけのたびに実施しています。行き慣れたところ以外へ出かける時は全て実施している形です。それを繰り返していくと次第にスケジュール策定の精度があがっていきます。それに合わせて子どもの段取り力や計画力も向上しているように感じます。
いまではタイムスケジュールを作成するのは、お出かけ時における子どもの役割になっており、お出かけ前の楽しみのひとつとなっています。
そのときの状況や条件を加味しながら段取りできるチカラは、試験当日の過ごし方のような短い時間でも、受験日までの過ごし方のような長い期間においても活用できると思います。いまは1〜3日までスケールでの段取り・計画をすることができるようになってきていると思います。
今年は長い期間での段取りをつけれるように長期休暇等の過ごし方のスケジュール作りにトライしてもらおうと思ってます。