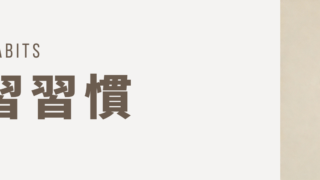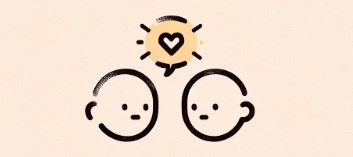時間を制すものが中学受験を制す(…だけでなく人生を制す)

突然ですが試験は何との闘いでしょうか?
ライバル…?、過去の自分…?、苦手な問題…?
答えは「時間」です。
わたしが思うに中学受験において時間を制すということは「制限時間内に全ての問題を解く」という基本的なところから始まり「時間内に集中力を途切れさせない」ことができるようになり最終的には「限られた時間で全力を出す(時間が余った場合は見直しで時間を使い切る)」ことができるということだと思っています。
この高みを目指し、うちでは、日常的に時間を意識させるように以下の工夫をしています。
勉強中に「時間」を意識させる
毎日の学習時間では時間を計測しています。テキストによっては目標時間が記載されているものは制限時間をセットして学習をしています。また計測した時間は実績として記入するようにしています。
目標時間の記載がないテキストもあるので、その場合は、単に時間を測るだけです。ただ毎日時間を測っていると大体の所要時間がわかってくるのと、学習中に意識が他に向いてしまったときのタイムロスに気づくので、結果的にダラダラやらず、時間で律することができます。
なお、時間計測には「セイコークロックの時計」(百マス計算でも使える)を使っています。
時計は何でもよいかと思いますが、この時計は子どもにも見やすいアナログ時計がついていて、タイム計測を簡単に設定しやすいボタン配置になっています。
毎日のタイムスケジュールを意識させる
これは毎日の生活を規則正しくしていった結果として自然にできるようになったことですが、子どもには毎日のタイムスケジュールを意識させるようにしています。
単純な話ですが、起きる時間、朝食の時間、学校の時間、帰ってくる時間、宿題の時間、おやつの時間、夕食の時間、寝る時間を子どもに意識させます。
そうすることで子ども自身で自分の自由な時間を作るために自発的にスケジュールコントロールするようになります。
この習慣を定着化させるために意識したことは親も規則正しくできる限り決められたスケジュールで一緒に生活する、ということです。親だけが夜更かししたりと時間にルーズだと定着化はしにくいと思います。もちろん忙しいときもありますが、それでもできる限り時間をコントロールして不規則にならないようにしてます。
時間を制すか?支配されるか?
「時間」を制すというのは実践しようとすると大人でも難しいテーマです。実際「時間」をコントロールできてない大人はたくさんいます。大人でも子どもでも本当にやりたいことを自己実現するためには「時間」のコントロールが必須です。(このテーマが気になる方は「夢をかなえるゾウ」読んでみてください)
ただ「時間」の扱いというのは難しいもので試験のとき「時間」を意識した結果、焦らなくなればよいのですが逆に焦ってしまうこともある。それで力が出しきれないこともある。
つまり意識しすぎない程度に意識し、進捗に対して時間が足りない場合はその場で対策を決めるところまでいかないと時間を制しているとはいえず、逆に支配されてしまうこともありえます。
人生、時間との戦い。その第1歩が中学受験。将来的に時間を制する大人になれることを願いながら1歩目のクリアを目指したいと思います。(自分も時間を制する大人であれるように…)