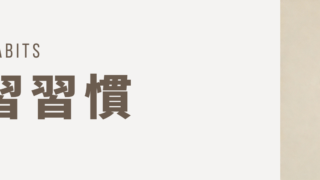料理を通じて前提条件から完成形をイメージして段取りできるようになろう

算数や理科では段取り力(条件を整理して段取りを考えるチカラ)が必要と言われます。
段取り力を向上させる方法は日々の学習だけではありません。日常生活でも段取りを考えて進めないとならないことが山ほどあります。そういったことを子どもに手伝ってもらうことで自然と段取り力の向上につなげられることが理想です。
段取りを考えないとならないモノゴト、その代表例は「料理」です。
小学生(低学年)だと、献立全品やすべての工程を担当することは難しいので、うちでは以下の範囲を任せることが多いです。
- 火を使わずにできるもの(主にサラダ)を任せる。
- サラダは、その日冷蔵庫にある野菜を自由に選んでもらう。
段取り力を養うことを目的としているので、うちでは料理の内容にはこだわらずに比較的安全・簡単にできるもの(主にサラダづくり)を任せることが多いです。
たかがサラダづくりでも、その日冷蔵庫にある野菜(前提条件)から完成形をイメージしながら、好きな野菜を選び、各工程を進めてもらうことで段取り力(条件を整理して解いていく順番を決める)を養うことができます。
各工程も限りあるキッチンスペース(前提条件)を使って「まな板を出す」「野菜を洗う」「野菜を切る」「ざる等に一時的に置く」「まな板を片付ける」「盛り付け皿を出す」「盛り付ける」の順番を試行錯誤しながらやってもらいます。順番を間違えると作業スペースが足りない、盛り付け(完成形)がイメージと違う、という問題が起こりますが問題も含め、そのまま体験してもらいます。
初めのうちは失敗もたくさんありますが、次第に自分なりの段取りを見つけ手際がよくなってきます。
また繰り返し実践した後の副次効果として、野菜の種類を覚えるようになります。その結果、野菜に興味が湧くことによる家庭菜園へのトライや、スーパーでの買い物時における物価変動への気づきにつながっていきます。


うちで実践している料理(というかサラダづくり)、はじめは嫌々手伝うような時期もありましたが、現在は子ども自身が楽しんでやってくれており、親は手伝ってもらって助かり、そして段取り力も向上するという一石三鳥な状態になっています。
1点だけ心がけているのは、料理という手間がかかることを誰かひとりに押し付けるのではなく、家族全員で分担しながら楽しんやるという雰囲気づくりをするようにしています。