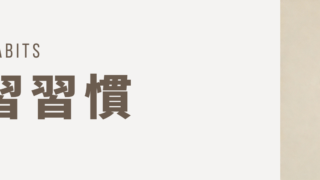学習した知識を自分事にできる絶好の課外活動、それは買い物

先日記事にした25年度の適正検査の内容のとおり、適正検査を突破するためには4科(国語・算数・社会・理科)の教科書に載っていることだけを理解しているだけでなく、これらの知識が身近な話題とつながって自分の考えを述べれるようになる必要があります。

つまり机上で学習した内容を現実社会を通じて自分事にすることが重要です。うちでは、日常的に発生する買い物に子どもを連れ出すことで社会体験させています。
具体的には以下のようなことを実施しています。(スーパーマーケットの場合)
- 買うものリストを渡し商品を探させる(例:野菜や魚、加工品などなど)
- セルフレジでレジ打ちと商品のカゴ入れをしてもらう
まず買うものを探すことで様々な品物(名前や形状など)を広く知ってもらうようにしています。一例をあげると、野沢菜(地域の名産品)、春の七草(それぞれの草の名前)、高野豆腐(鎌倉時代にできた加工品)等です。品物の名前をたくさん知っておくことで国語や社会の文章でこれらの名詞が出てきたときにもその文章の理解がしやすくなると思います。
また定期的に品物を見ておくことで、それらの値段も覚えられるようになります。そうなると、いま何が高く安いということがわかるようになります。電気やガスの燃料費が高騰に比例して物価が上がっているというニュースが肌感覚で理解できるようになります。結果、いまのニュースが身近な話題として消化できるようになります。身近な話題が自分にとって不利益な事象になっていたら、それをどうやったら解消できるかを考えるキッカケにもなると思います。
もうひとつのやっていることであるレジ打ちと商品のカゴ入れですが、これはレジ打ちしたものをどうやってカゴに入れていくかを考えることで段取り力の向上につながります。はじめのうちは全ての品物が1つのカゴに入り切らないことが多くありますが回数をこなしていくうちに固く四角いものは角に置く等、子どもなりに正解を見つけていきます。
親の買い物に着いてくるだけ(見ているだけ)だと子どもにとっては退屈な時間でしかないのですが子どもにやってもらうことで全てが学びになります。何より子ども自身がとても楽しみながら買い物をしてくれますし、結果的に親も買い物が楽になるという両得な状態になります。