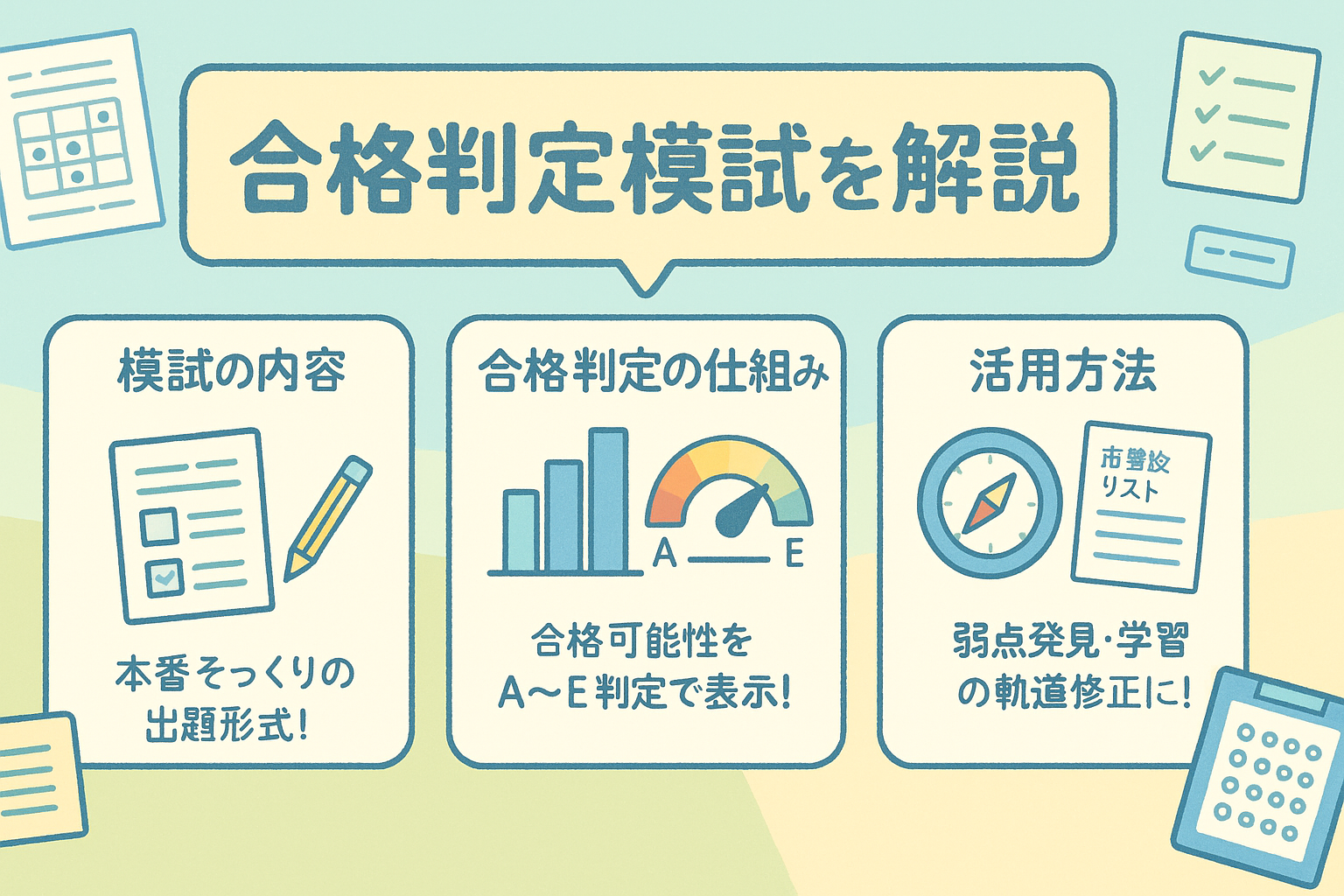25年度 都立中適正問題の総括
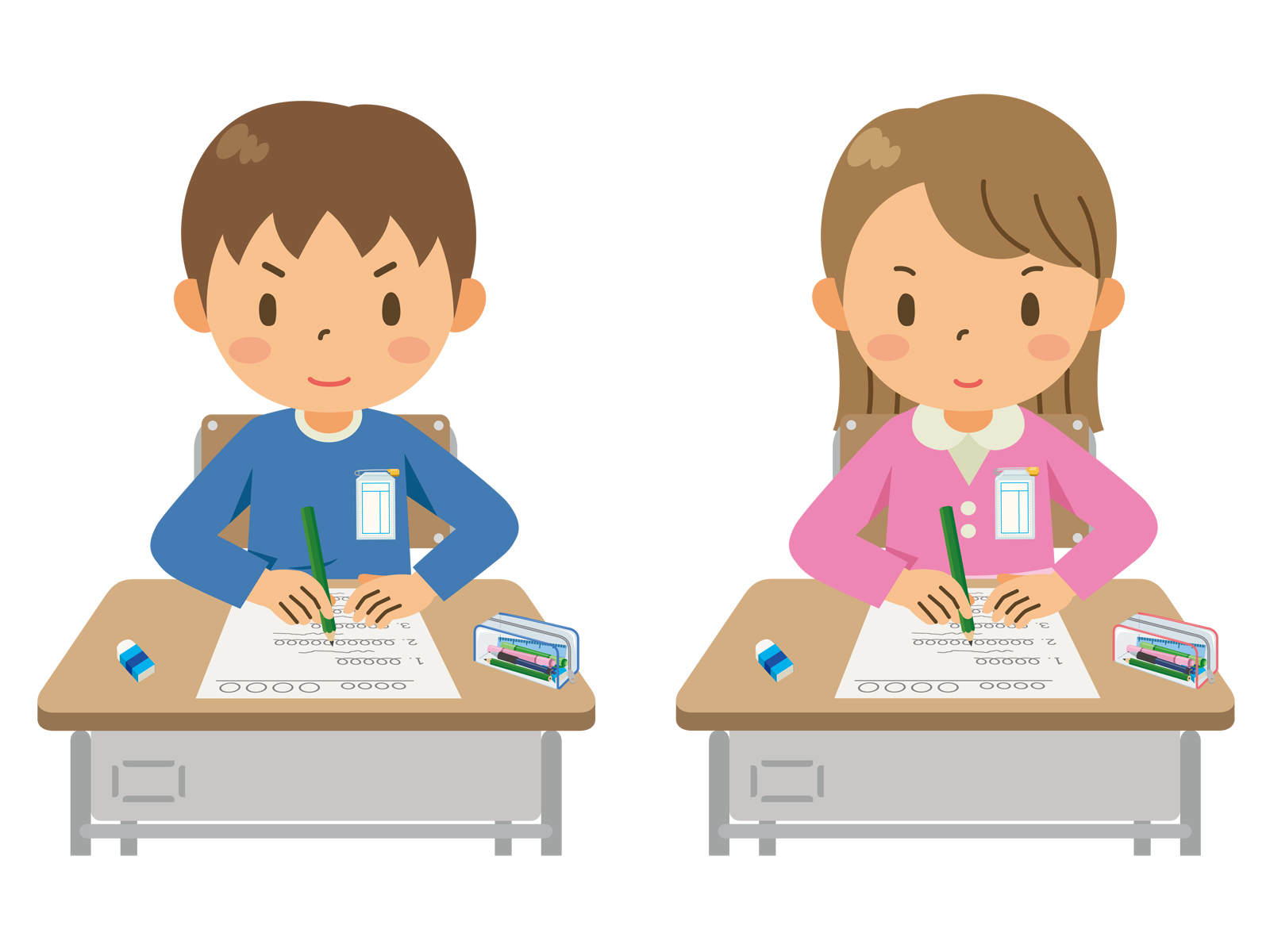
ご存じのとおり、2月3日に都立中の適性検査が実施されました。
各塾からも25年度の適性問題の解説が出始めています。うちの子も3年後に受けるテストゆえ、わたし自身の目でどんな問題が出されているのかを確かめておこうと思い、初めて問題と回答内容を確認しました。
塾では小学6年生になるまでは問題は見なくて大丈夫、と言われているのですが、先に到達点を知っておくことは大事かなという判断をしました。
適性検査は各学校とも共通問題と独自問題の組み合わせで構成されています。ここでは小石川中の問題を総括します。
適正検査Ⅰ
適性検査Ⅰは国語・作文問題です。25年度は大きく分けて「読解問題」と「作文問題」が出題されました。
読解問題
課題文を読み、その中から設問にあった文節を解答するいわゆる穴埋め問題です。現時点(新小4)でも似たような問題を実施しているので案外解きやすい問題と感じます。
ただ解答の候補となるところが複数出てくるため正解を絞り込む根拠を探す力が必要です。
作文問題
その名のとおり作文です。自分にとっての「謎」は何か、そしてそれを解決するためにどのように取り組んでいるかを400字で述べるという問題です。
限りある時間の中で、どういったテーマをどういう流れで書いていくかを考える構成力、それを時間内で書ききる記述力が必要です。こういったチカラは作文の訓練を繰り返しすることで鍛えられます。逆に言えば事前に訓練していないと制限時間内に設問意図に沿った作文はできません。(開始数分でテーマを決め、そのテーマに対してどういった構成にするかの下書きをし、それから書き出す、を繰り返ししておくことが重要です)
構成力と記述力は作文問題を解く基礎となるチカラです。その土台があった上で最後にして1番重要なチカラは、試験当日に始めて知らされるキーワードに対してどういったテーマを主題に置くかの引き出し力です。
この引き出し力は、基本的には自分が経験したこと(読書などで疑似体験したこと含む)の量に比例します。自分の頭の中に鮮明に残っているテーマであればあるほどスムーズに作文ができます。逆を言えば経験してないテーマは表面的には作文を書き始めても細部まで丁寧に書き切れないために指定文字数に到達できず最後に失速するということが起こります。
enaでは小学6年生での日曜特訓で作文の訓練を行いますが、それまでの期間で自身でできる訓練としては日記(週1回、その週であったとことを整理して書く)が良いと思います。
また日曜特訓では引き出し力の強化まではできないと思われるので、このチカラは別途高めておく(引き出しのネタを蓄積しておく)必要があります。
適正検査Ⅱ
算数・理科・社会の複合問題です。25年度は大きく分けて「図形問題」「データ読み取り考察問題」「実験結果の考察問題」が出題されました。
図形問題
展開図から面積を求める問題や、立体を組み合わせる問題です。内容は6年生の水準になっていますが、こちらも現時点(新小4)で似たような問題を実施していることもあり、6年生までに同種の問題を繰り返し練習しておけば解ける部類と感じます。
データ読み取り考察問題
計算結果をもとにグラフを作成する問題や、資料にある情報から関係性を考察する問題です。複数の資料から関連性を読み取るチカラが必要です。日頃からデータを読み取る訓練をしていないと短時間で解くのは難しいかもしれません。
また社会の知識(今回の例だと環境問題に関する知識)をもとに課題解決策を150字で記述するところがあり、幅広い知識がないと筆が進まないであろう問題もありました。
実験結果の考察問題
理科の実験結果をもとに事象を考察する問題です。実験結果から事象を科学的に説明できるチカラが必要です(例:空気入れを押した回数が多い→空気が多く入っている→体積が大きい)日常生活を通じて無意識に理解している事象を適切な言葉で説明できるかがポイントです。
適正検査Ⅱから言えることは、社会・理科の知識そのものを問う設問は出ませんが、各単元の幅広い知識とそれを身近な話題として説明できるチカラが必要ということ。したがい、社会・理科は知識学習だけでなく、その知識が現実社会でどのようなことにつながっているのかを実感する課外学習をしておくと役に立つと思います。
適性検査Ⅲ
理科と算数の問題です。25年度は大きく分けて「身の回りの現象に関する考察問題」と「模型を動かしたときの軌跡について説明する問題」が出題されました。
さすが都立中最高峰の試験。正直、大人でも難しいと感じる問題です。現時点(新小4)では、この問題の内容を踏まえた準備をしようがないと感じたため詳細を解説するのは割愛します。物質(気体・固体・液体)の特徴や、図形の性質などがわかってないと話にならないです。したがい、いまは理科や算数の知識習得を広げ、その後、具体的な対策として子どもの学習プランに繋げられる状態になったら改めて解説したいと思います。
適正検査Ⅲは、そもそも設問の前提となる知識がないと答えを考えることすら難しい問題が多い印象でした。知らないと考えも及ばない。知っていれば、そこを切り口に思考を巡らせることができる。ゆえにまずは様々な知識を蓄えておくことが重要と感じています。
あと3年でこの極みまで到達できるか…、到達までの道のりを行く楽しみを持ちながらも計画的に学習を続けていきたいと思います。