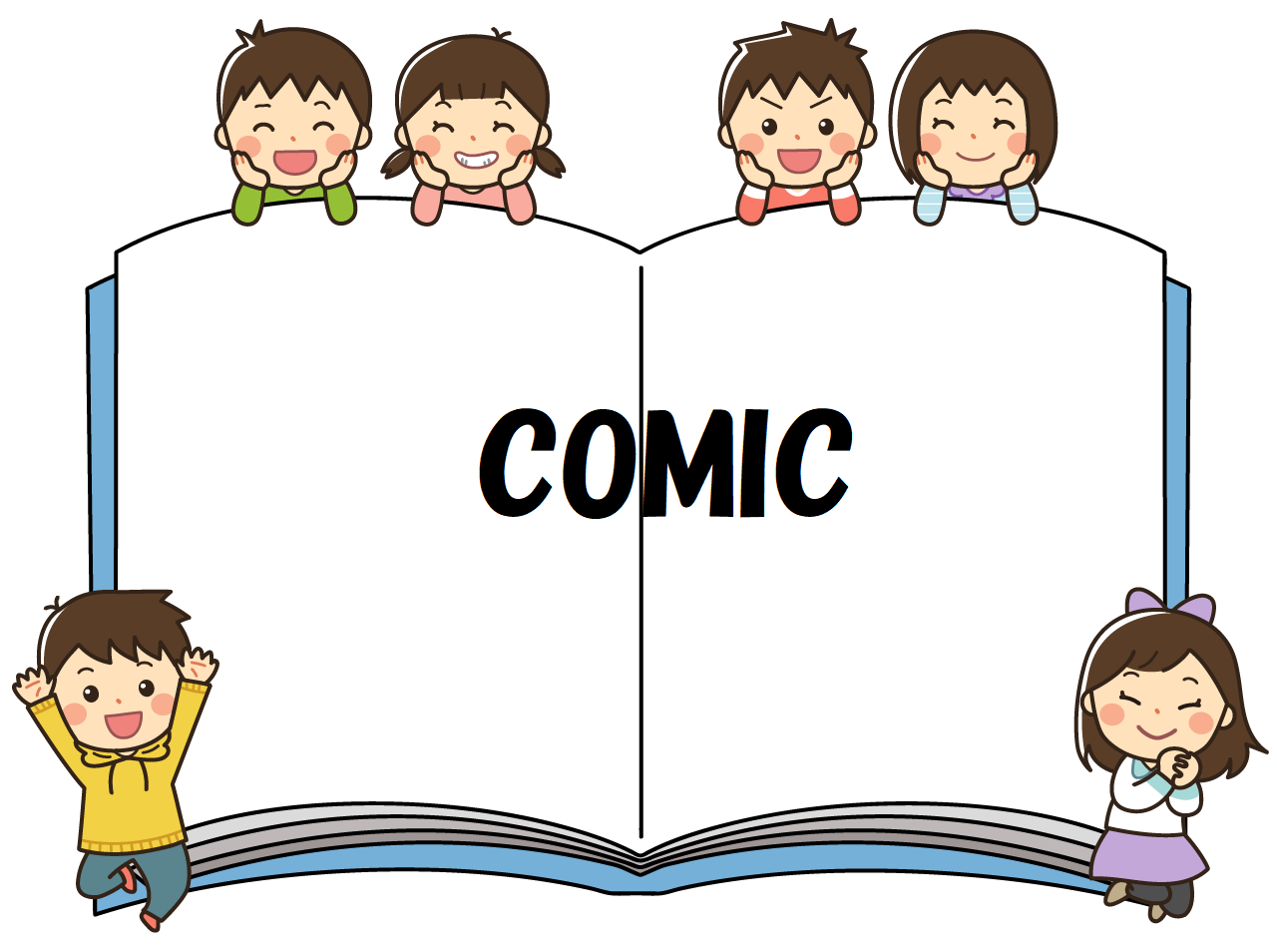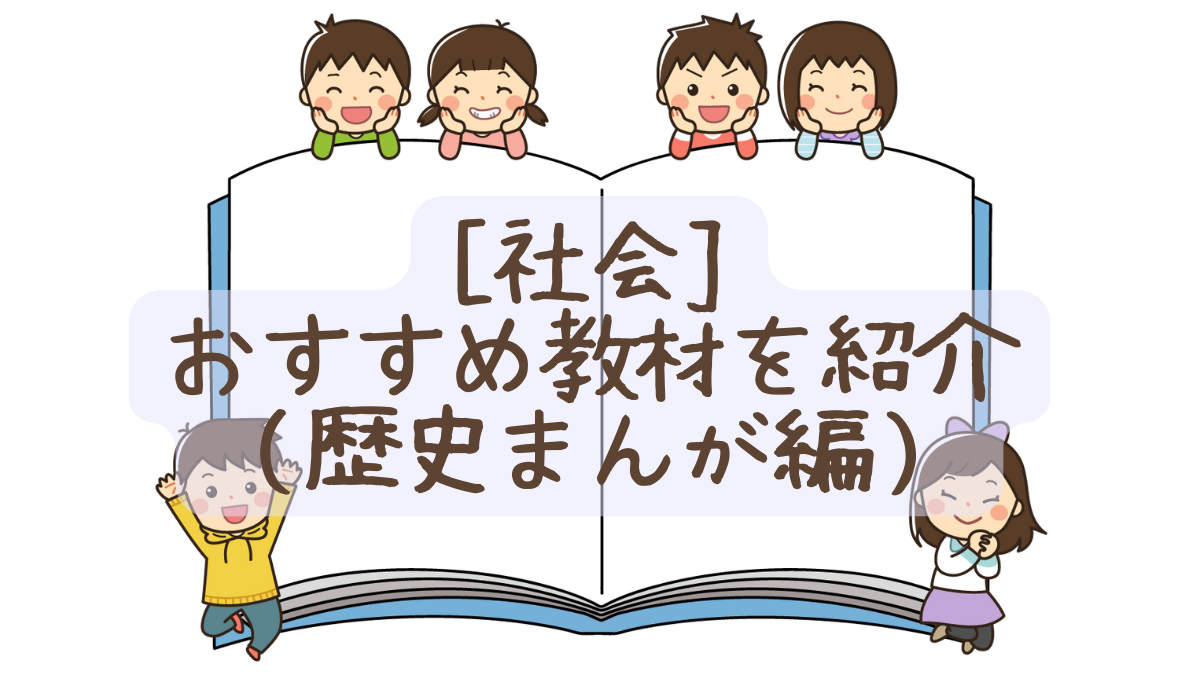小4 社会教材2(小学歴史年表)
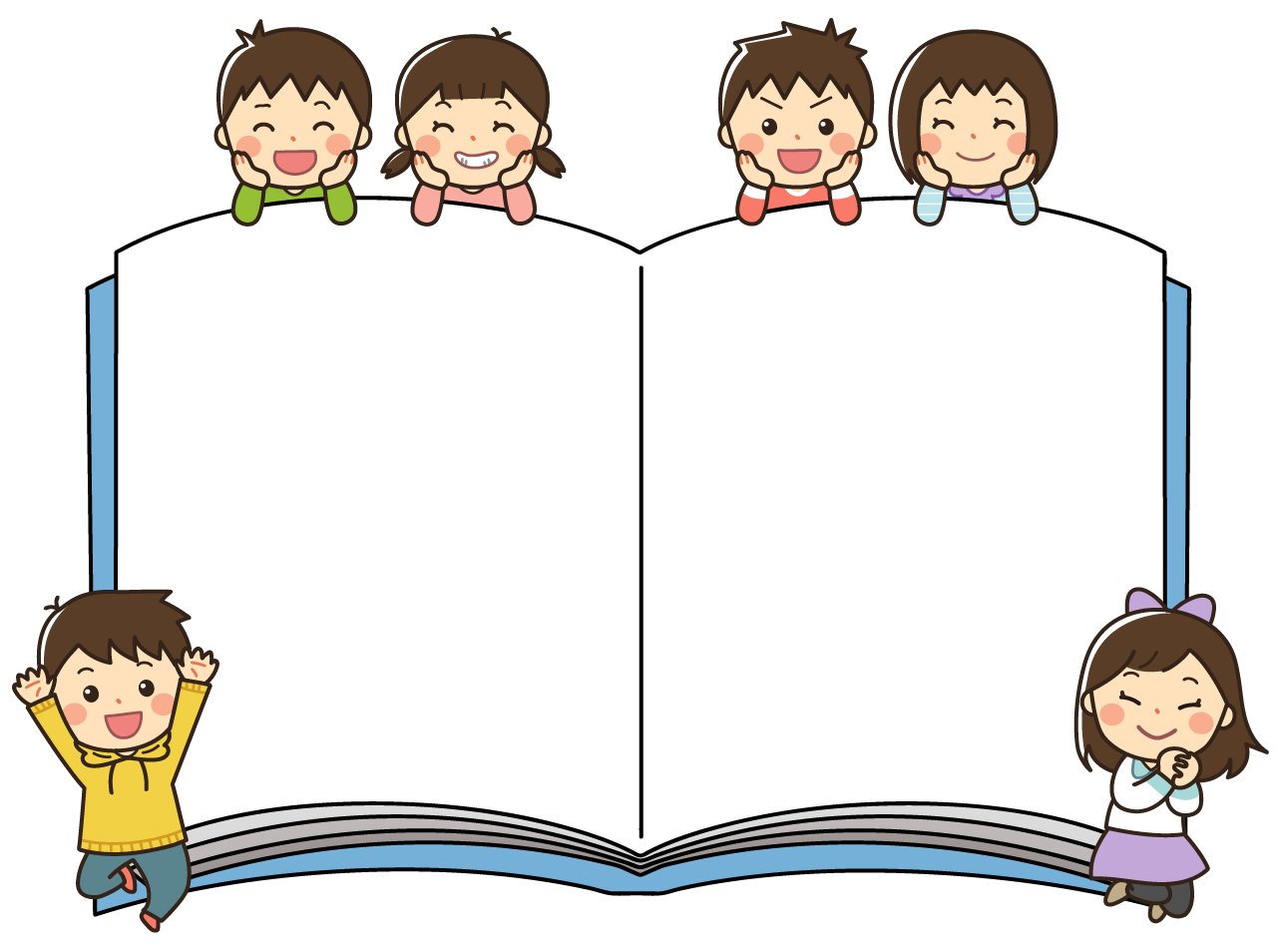
歴史を単純な暗記にしないようにするには歴史の流れ(過去の出来事があり、その結果いまがある)を理解しておくことが大事だと言われます。
この歴史の流れの全体像を理解するための教材は世の中たくさんあります。スタンダードな参考書、問題集から始まり、遊びで覚える歴史クイズカードゲーム等々。うちでも歴史の学習を始めるにあたり入門教材としては、どのような教材が良いかを考えました。
結論、うちでは、JTBパブリッシングの「小学歴史年表(学習ポスター)」にしました。
小学歴史年表から始めた狙い
歴史学習の入門としてやりたかったことは、以下2点です。
- 旧石器時代から長い歴史があり現代に至るという全体感を理解する
- その長い歴史のなかで、子ども自身が1番興味が湧く時代を見つける
ひとつめの「全体感を理解する」は、2000年余りの歴史の壮大さを実感してもらうことです。年表は参考書にも記載されていますが、B5見開きの狭いスペースに細かく書かれていることが多いです。この小学歴史年表はサイズ横78.8cm×縦54.5cm 2枚の年表であるため、歴史の壮大さが感じやすいです。また文字が大きいため、すべての情報に目が届きやすいという効果もあります。
ふたつめの「子ども自身が1番興味が湧く時代を見つける」は、深堀学習の入口になる場所(時代)を探すことです。歴史の学習は入る場所を間違えると、ただ退屈な内容という印象を与えてしまいやすい教科だと思います。また適切な場所というのは、各人によって異なります。興味を持てば詳細を調べるために参考書を開くこともあると思いますが、興味が湧く場所を探すのに分厚い参考書を開くというのは手軽じゃないと感じます。ましてや分厚い参考書の開いたページに興味が湧かなければ、次第に参考書を開くことがなくなるといったことにつながってしまいかねません。
この小学歴史年表ではページ上段に歴史年表と主な出来事が記載され、下段には歴史上の人物の紹介が記載されており、子ども自身が興味が湧く時代(事柄・人物)のキーワードが目につきやすい構成になっています。
この小学歴史年表を平時、視界に入りやすいリビングに貼り付けることで、歴史の全体感を理解し、深堀学習の入口を見つけようとしています。
(なお、平時、視界に入りやすいところに教材を貼っておくというのは、以前ご紹介した受動的暗記と同じ手法になります。)

教材の使用感
まずリビングに貼ったことで、定期的に年表を見る時間ができました。歴史の全体感(各時代が何年くらい続いたのか等)を覚え始めています。
また年表に記載されている事柄や人物は、まだ未学習の領域であるため子どもからしたらほとんど聞いたことのないものばかりですが、その中で知っているキーワードを見つけると、そのキーワードと時代とを関連付けして知識定着が始まっています。
例えば、これまで歴史上の人物の伝記として読んだ「伊能忠敬」が江戸時代の人物だった。江戸時代にはまだ地図というものがなかった。という情報が関連付けられ、江戸時代に興味を持ち始めてます。
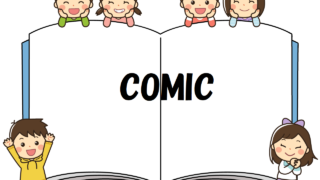
うちでは、この年表から子どもの興味が湧いた時代を生きた人物の伝記を読むということで歴史学習を進めていきたいと思っています。