小4 算数教材1(百ます計算)
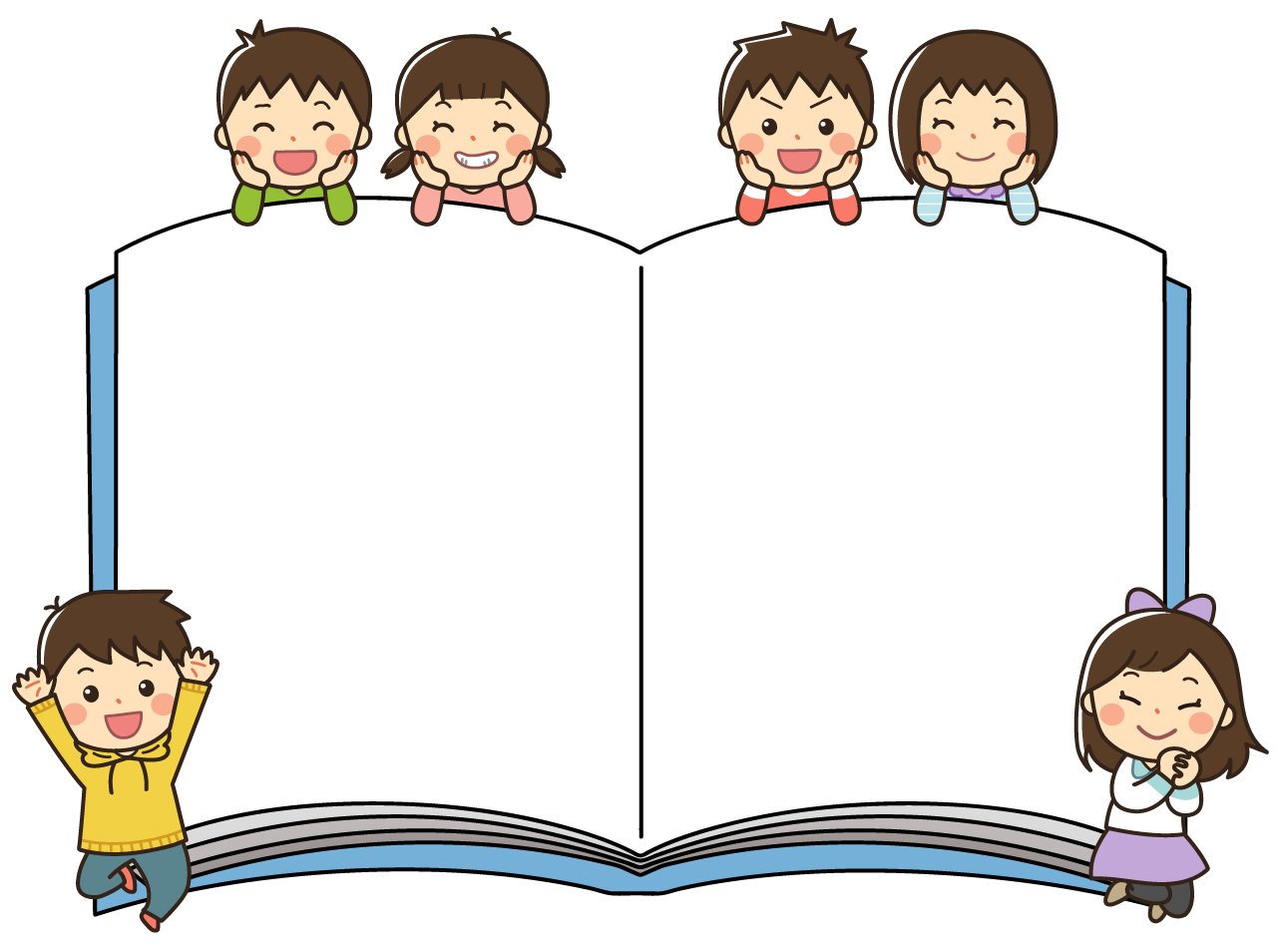
算数力をあげるためにもっとも基礎になるのは計算処理力です。
計算処理力とは四則演算の正確性と処理スピードです。2桁の掛け算や割り算を暗算並みのスピードで計算できる子とそれ以外の子では、単純な計算問題を解く時間に差が生まれます。そして、そこで積み重なった時間の差は、テスト後半に出てくる本来時間をかけるべき文章題にかけられる時間の差として表れます。
計算処理力はテクニックというより基礎体力のようなもので、日々の積み重ねで少しずつ養われていきます。計算処理力を向上させるために、低学年で計算ドリル(単純な計算問題)に取り組んでいる子は多く見られます。
ただ高学年になるにつれ、文章題や応用力が必要な実践的な問題に取り組む頻度が多くなり、単純な計算問題をこなす機会は減っていきます。計算処理力向上のトレーニングは筋トレのようなものでやらなくなると次第に衰えてきます。
うちの子も応用問題を解くようになってから単純な四則演算を繰り返し解く機会が減ったせいか、応用問題の解き方は合っているもののひっ算での計算ミスをすることが目立つようになってきており、改めて計算処理力の向上と維持の必要性を感じてきています。
計算処理力トレーニングの代表格といえば「百ます計算」です。
百ます計算は、1分間(短時間)で、できるだけの多くの計算を正確にこなすトレーニングです。8種類が4回分収録されており1日1ページを実施すると128日(約4ヶ月)で消化することができます。この算数脳の筋トレを中学受験まで毎日継続したら、いやでも計算処理力が高まると思います。
うちでは毎日3問計算を実施していることもあり、比較的単純な計算力はあるだろうということで「百ます計算2」を実施しています。「百ます計算2」はタイトル通り2桁と1桁の四則演算になります。100問を5分以内に解けないようであれば「百ます計算1」から実施するというのが基準です。
うちの子の場合、足し算、引き算は問題ないレベルですが掛け算以降は5分以内で解けないかもしれず、その場合は掛け算、割り算だけ「百ます計算1」を実施するというように併用する形で教材を活用していこうと考えています。



