小3 国語教材11(お米は生きている)
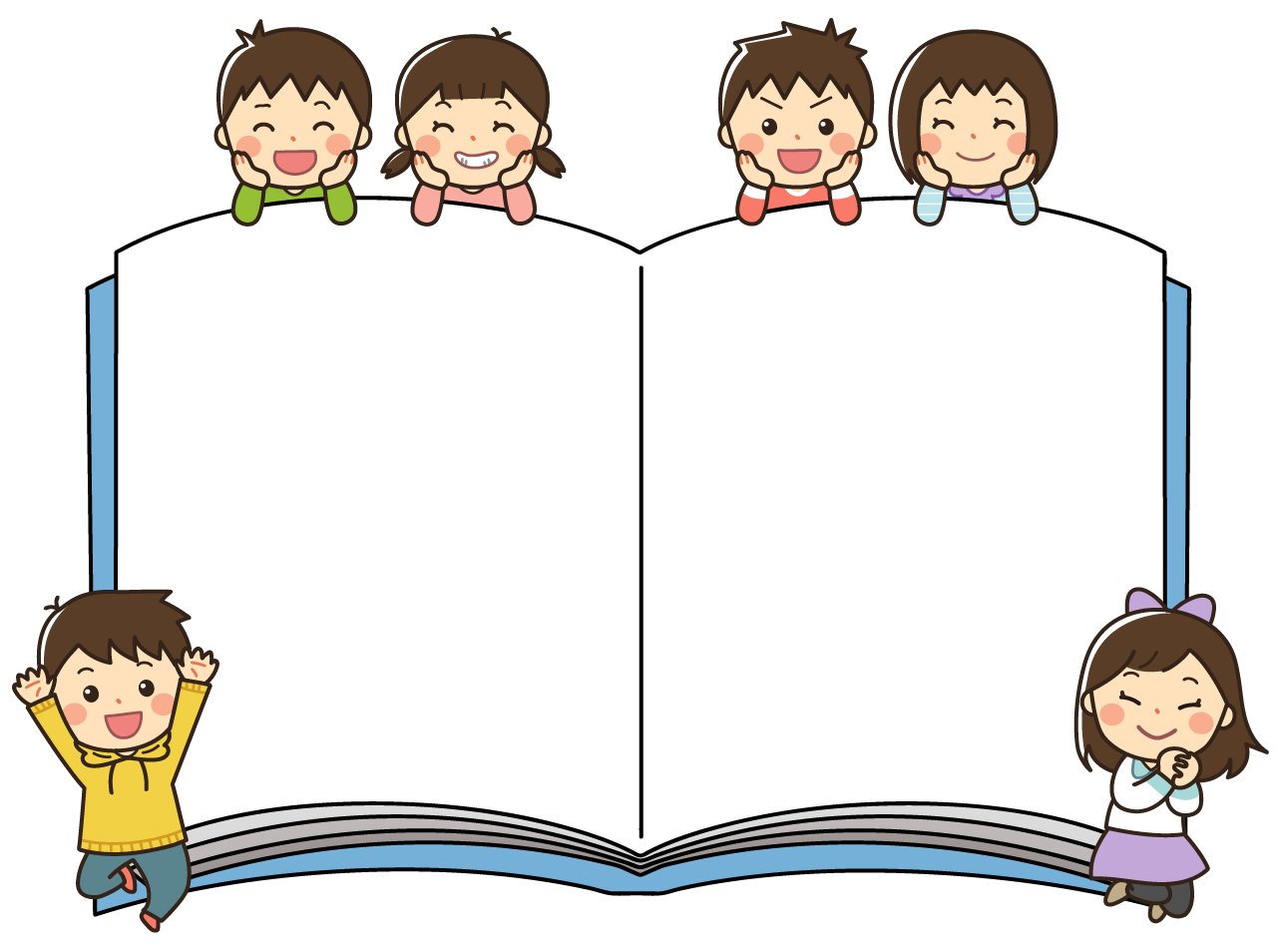
うちでは学習習慣をつける取り組みとして、毎日読書する時間をつくっています。

塾に通う前(未就学〜小学2年生)までは読む本を手当たり次第、図書館から借りてきていましたが、塾に通うようになってから読む本の選び方が変わってきました。
その選び方とは「塾のテキストや模試に出題された」本を選ぶということです。
今日は「お米は生きている」を紹介したいと思います。
書籍の概要
日本人にとって「お米」とは何か?を紐解く話です。「お米」とは単純に食べ物というだけではなく、日本の文化の真ん中にある大事なものだったのです。身近だけど壮大な「お米」にまつわる知識が得られるノンフィクション書籍です。
この本の一節が塾のテキストで長文問題として出題されました。
本の感想・学び
この本は150ページ超の大作ですが、文字が一般的な文庫よりも大きく漢字にはカナが振られ、2,3ページ毎に挿絵が入っている等、小学生がひとりで読み進められる工夫がされている本です。ただ内容は地名や歴史上の人物名、低学年では理解が難しい言葉も多分に使用されていることもあり、ひとりで最後まで読むのはしんどいかもしれません。うちでは子どもと一緒に読みました。
この書籍は実は「自然と人間 生きているシリーズ」(全5冊)刊行されているうちの1冊になります。日本はコメ食離れが進んだ結果、日本の川も森も、海もすべてが悪い方に向かっている。ということに警鐘を鳴らしています。著者の主張がシリーズ全体でのメッセージになっています。
そういうことからも、本書とこのシリーズを読むことによって、日本の文化の総合的な知識が得られます。(農業、自然、食)
1個1個の知識は、今後の社会科目で役に立つと思うし、全体を俯瞰した社会課題に関する知識は、適性検査の作文の引き出しの1つになるだろうと思います。
量・内容ともに重厚になりますが、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。


