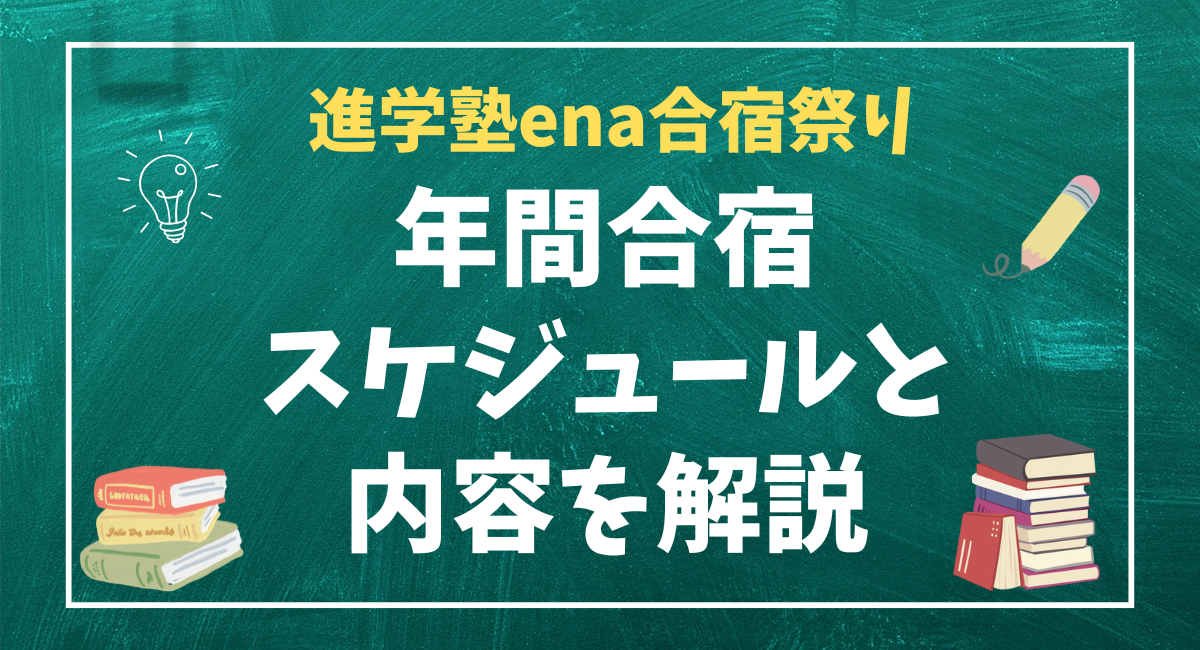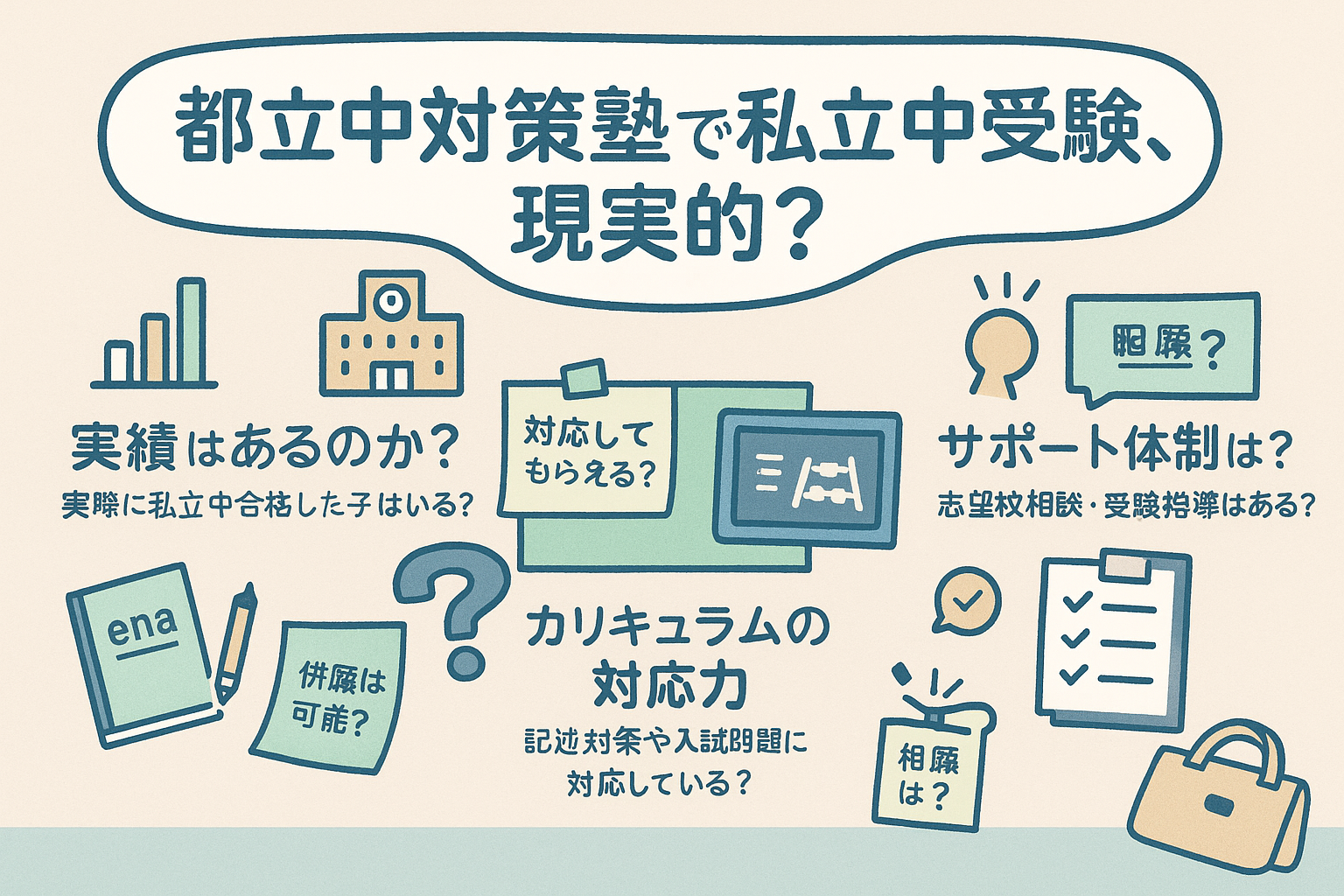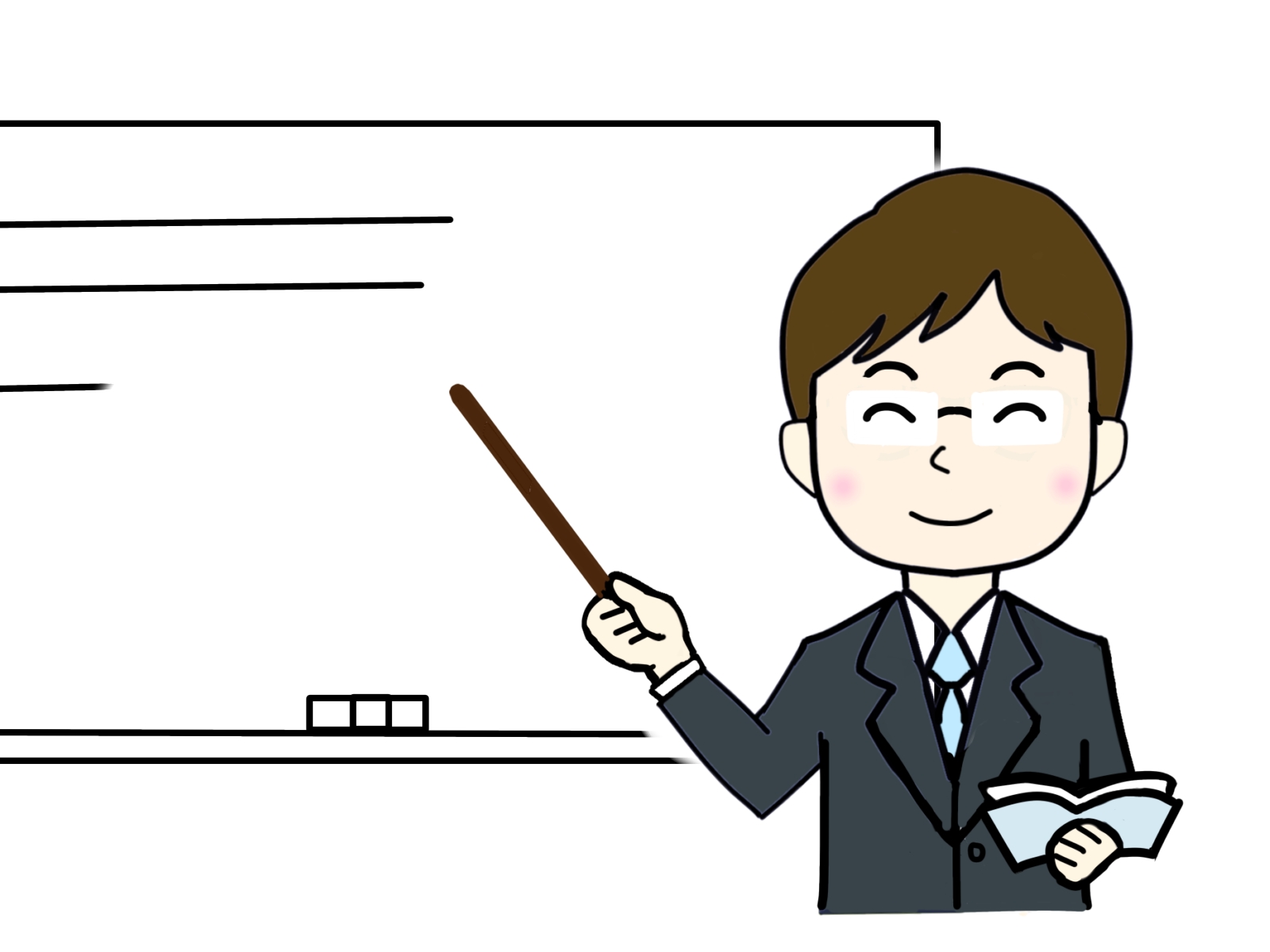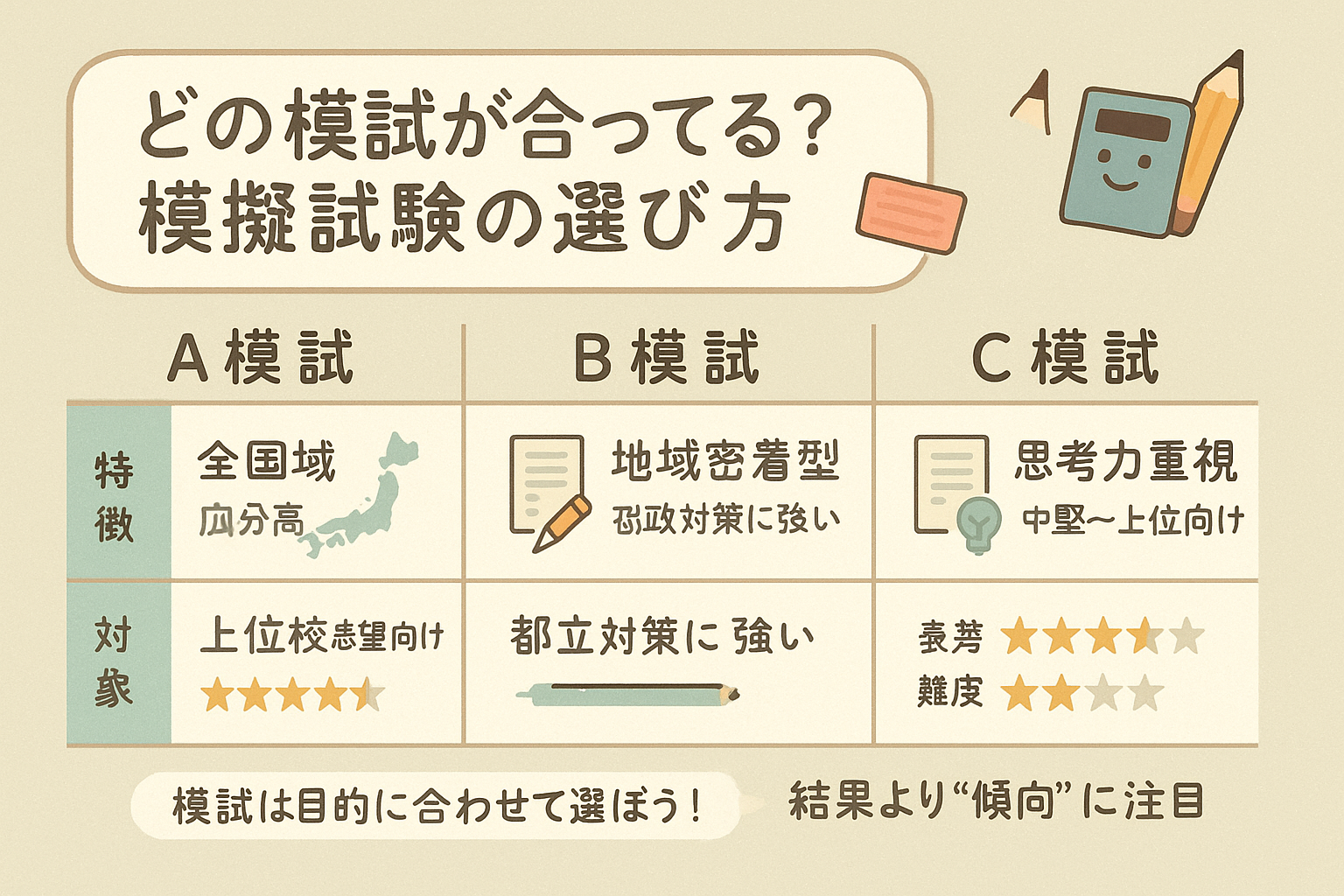文春に取り上げられた22泊夏期合宿の舞台裏に関する考察
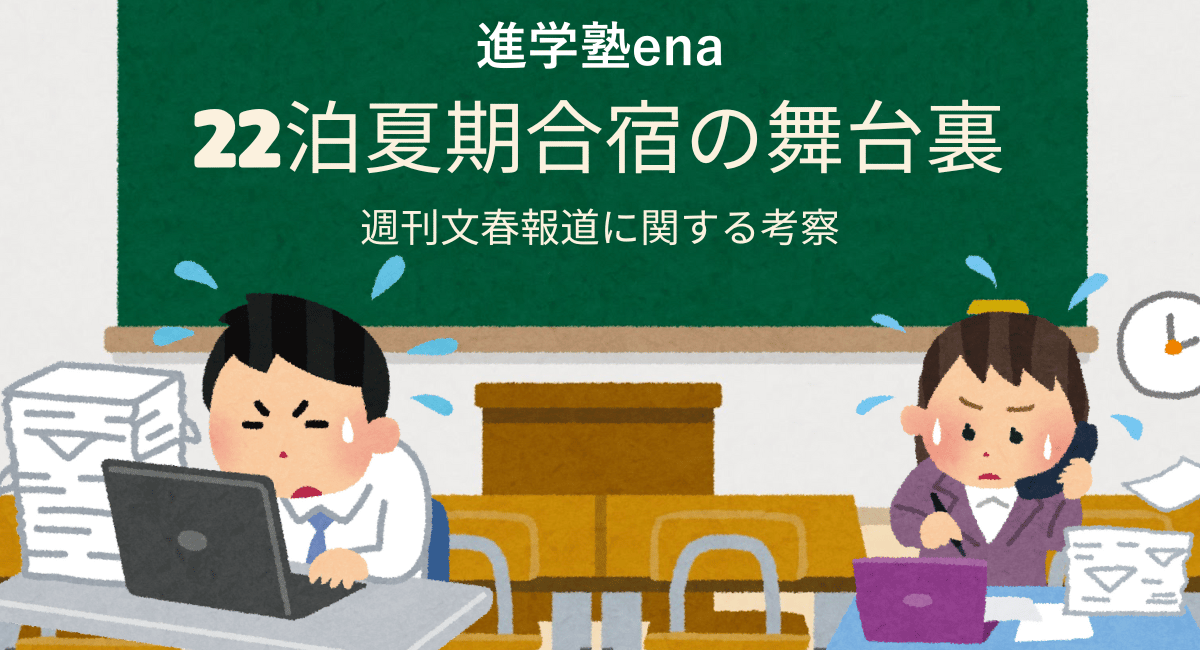
今回はenaの夏期授業の実態の解説と、文春に取り上げられた22泊夏期合宿の舞台裏報道について考察したいと思います。
22泊夏合宿 舞台裏に関する報道
今期より夏期合宿の超長期コース(22泊23日)を発表して話題となったのは記憶に新しいと思います。

そんな進学塾enaですが、その舞台裏について先日、文春オンラインにて報道されました。
【内部告発多数】進学塾ena 異例の「22泊23日夏合宿」の裏で大量退職が起きていた!(Yahoo! ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/47fa4fd4ba592fdfbb34e9d44e1164e7f0e50f18
報道の概要としては、22泊23日の夏期合宿の裏では、社員の大量退職と法令違反が起きており、高額な授業料に見合った教育を提供できていない、という内容です。
いわゆる「文春砲」の類です。(文春砲自体の批評をするものではありません)
うちの子は、今年の22泊合宿の対象学年ではなかったため、その話題の合宿には参加していませんが、一方で、夏期講習に参加する傍ら、本科の生徒として進学塾enaの夏期授業の実態を近いところで見てきたと思います。
今回は、夏期講習の受講生からみた進学塾enaの夏期授業の実態を解説し、今回の報道に関する所感を述べたいと思います。
25年度の夏期授業の実態
以降では、25年度の夏期授業の実態について解説していきます。
夏期授業スケジュール
うちの子は、夏期講習に参加していました。
進学塾enaの夏期授業(8月授業)は大きく「夏期講習」と「夏期合宿」で構成されており、通常授業はありません。
各学年で提供されている合宿のコースは以下のスケジュールで構成されています。
| コース | 夏期講習 | 夏季合宿 |
|---|---|---|
| 小4、小5夏期合宿(4泊) | 7/27〜7/31、8/2〜8/6、8/8〜8/12 | 7/21〜7/25 |
| 小6夏期合宿(10泊) | 7/21〜7/25、7/27〜7/31、8/2〜8/6、8/8〜8/12 | 8/14〜8/24 |
| 小6必勝合宿(22泊) | 7/21〜7/25、7/27〜7/31 | 8/2〜8/24 |
また夏期授業の参加者が少ない校舎では、別の校舎と合同での開催になっており、通常期間よりも1クラスの人数が少し多めでの授業になります。
ena社員(プロ教師)の講義でクオリティが高い
うちの子が受けた小4夏期講習(4科)は、15日間の授業のうち、すべての授業がena社員(プロ教師)による講義でした。
さらに重要科目である算数はすべて校長による授業でした。
通常期間(8月を除く各月)の授業ではアルバイト教師とプロ教師が混在しながら運営されます。
当然ですがプロ教師の方が授業のクオリティが高いため、プロ教師の頻度が高い方が受講生から見たら満足度は高くなることが多いわけですが、夏期講習は総じて満足度が高い結果となりました。
通常期間の授業のクオリティに関しては、以下の記事にて解説していますので、よかったらご覧ください。

受講生から見た今回の報道に対する考察
以降では、25年度の夏期授業の実態を踏まえた上での、今回の報道に関する考察を述べたいと思います。
ena社員にとっては過酷な夏休み
今年の小4夏期講習、受講生の立場としては満足度が高い内容でしたが、一方、教師目線で見るとハードな期間だと感じました。
今回、すべての授業がena社員による授業になったのは、夏期特有の事情に加え、今年初の長期合宿(10泊、22泊)の影響だと思われます。
通常期間と異なる事情というのは、以下2点です。
- 夏期休暇シーズンはアルバイト講師が休暇取得の傾向が強くなり、社員が対応しないとならない授業が増える
- 合宿は、ほとんどの社員も泊まり込みでの対応となる
つまり、通常月より8月はena社員のシワ寄せが高まる期間であり、かつ、今年は合宿期間の長期化に伴う拘束期間の長期化がありました。
合宿前の期間にあたる夏期講習期間中も、毎日の授業報告(メール通知)が来るのは、毎日22時頃になっており、その激務の大変さが想像でき、頭が下がる想いでした。
そのうえ、その夏期講習が終わると、そのまま10泊または22泊の泊まり込みの合宿へ突入するのだから、ena社員への負担はとても大きいものと想像できます。
昨年度までは、enaも小6を対象とした合宿は4泊5日が基本だったのに対し、今年からは最低10泊、最大22泊となったことが、生徒のみならずena社員にとっても今年最大の変化点だったと言えます。
ena社員(特に校長)に対しては感謝しかない
例年8月はena社員の負担が高まっている状況だと思われますが、今年は合宿期間の長期化に伴うの拘束期間の長期化があったことで、今回の報道につながったと思われます。
普通、どこの会社でも労働基準法を守らなければならず、上場企業である進学塾enaもキチンとした組織運営が求められます。
具体的には、労働基準法では週1日は休みを取得させなければならない、という基本ルールがあり、そこから考えても、10日連続勤務や22日連続勤務というのは通常は労働基準法違反にあたります。
なのになぜ、それを回避できるのか?
それは、変形労働時間制での運用(月に4回の休日を取ればOK)や、管理職者の労働基準法適用除外を用いているからと思われます。
おそらく、校長の多くは管理職ではないかと思われます。(想像です)
管理職者は、労働基準法の適用除外となり、労働時間・休憩・休日の規定は適用されません。つまり、校長を管理職者とすることで、22泊の泊まり込みでの仕事も可能になっているのではないかと想像します。
今回の22泊合宿。校長は必須参加(小6合宿者が集まる8/14週からの途中参加者も含む)と聞きます。それを裏付けるように合宿の期間(8/14以降)は、どこの校舎も基本的に閉鎖されてました。(いつも使える自習室が使えない状況でした)
会社として労働基準法に抵触しない運用をされていたとしても、22日間の連続勤務という状況は、普通に就業している身ならば、退職を考えたくなるような状況だと思います。
(補足:こういった就業環境は学習塾のみならず存在すると思います)
ただそんな過酷な状況下でも逃げずに、真摯に子供達に向き合い授業をしてくれたena社員(特に校長)には頭が下がる想いで、感謝しかありません。
ビジネス感のあるena、改革のしわ寄せは現場へ
報道されるのも納得できる過酷な状況、ただ他でもありそうな話
文春の報道の真偽は、私ども消費者にはわかりませんが、受講生として進学塾enaの夏期授業を見ていた限り、ena社員(特に校長)からすると、かなり過酷な就労環境であると言えると思います。
過酷な就労環境と思うのは、先に説明した「アルバイト教師が少なくなることによる社員への負担」と「22泊23日の拘束時間」という2点です。
一方で、報道されていた社内通達文書の内容(以下)は、これだけ切り取られると負のイメージを抱く方も多くいるかもしれませんが、会社としての目標を掲げ、社員を鼓舞し目標達成のために社員に全力を求めるというのは、経営としては間違ってはないとも思ってしまいます。
本部は、特に学院長は炎上上等くらいに思っています。つまり、言いたいことは言わせておけ。最後はenaがしっかり成功させて世の中を、他塾を見返してやる。(略)つまり、絶対に失敗はできません。
〜Yahoo!ニュースより引用〜
とはいえ実際、火のないところには煙は立たず。鼓舞の仕方には問題があったのだろうと思いますし、何より過酷な就労状況であったのは間違いないのではと思います。
他社との差別化・優位性を示そうとする経営陣
合格者実績水増し問題や、今回の件など、他塾に比べてなにかと業界を騒がさせることが多いのが進学塾enaです。
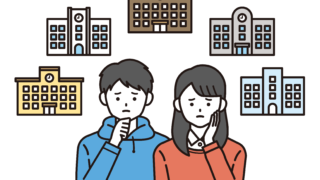
enaに限らず塾はサービス業であり営利企業です。それを追求するあまり、こういった負の側面が報道されてしまうということもあります。
でも裏を返すと、他社との差別化を図り、競争優位性を高めていこうという進学塾enaの経営陣の意思が見える場面でもあります。
ご存知のとおり、進学塾enaは都立中受験が流行り出す前から、いち早く都立中対策塾という分野を開拓し、消費者のニーズを捉え、いまや「都立中のena」のブランドイメージを構築した先駆者であり、ビジネス感があることは認めざるを得ないです。
市場のニーズを捉え、他塾に先駆けていち早く、ビジネス拡大戦略を打ち出し実行していく。そのビジネス感と実行力が結果的に、現場の指導方針や授業カリキュラムに露骨に影響が出てきてしまっているという状況だと思います。
その代表格が「都私立のenaへの転換」や、今回の「22泊の夏期合宿」です。
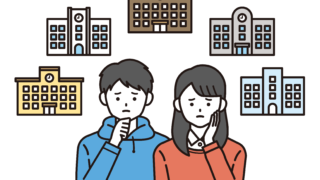
ビジネスの観点では、他社との差別化を図り、優位性を高めようする経営陣の姿勢は頼もしくも思えますが、時に、そういった改革には痛みを伴うこともあり、その痛みは現場の教師陣や生徒に及ぶという状況になります。
今回は、その痛みがena社員(特に校長)に重たくのしかかっていたと感じます。
そういった状況下でも会社の経営方針と現場の生徒の間を取り持ちながら支えてくれているena社員には感謝しかありません。
今回の夏期合宿の件で言えば、23日間を教師交代制にし、ena社員は週末には自宅に帰宅できるようにする等の運用をすることで、現場教師の負担も和らぐのではないかと思います。
そういった現場教師に対する配慮が結果的に、授業のクオリティ向上にもつながり、消費者である我々の利にもなると思います。
うちの子は2年後に小6となります。現時点で22泊の夏期合宿に参加する想定はありませんが、この先、この合宿がどのような進化を遂げるのか、引き続き見届けたいと思います。