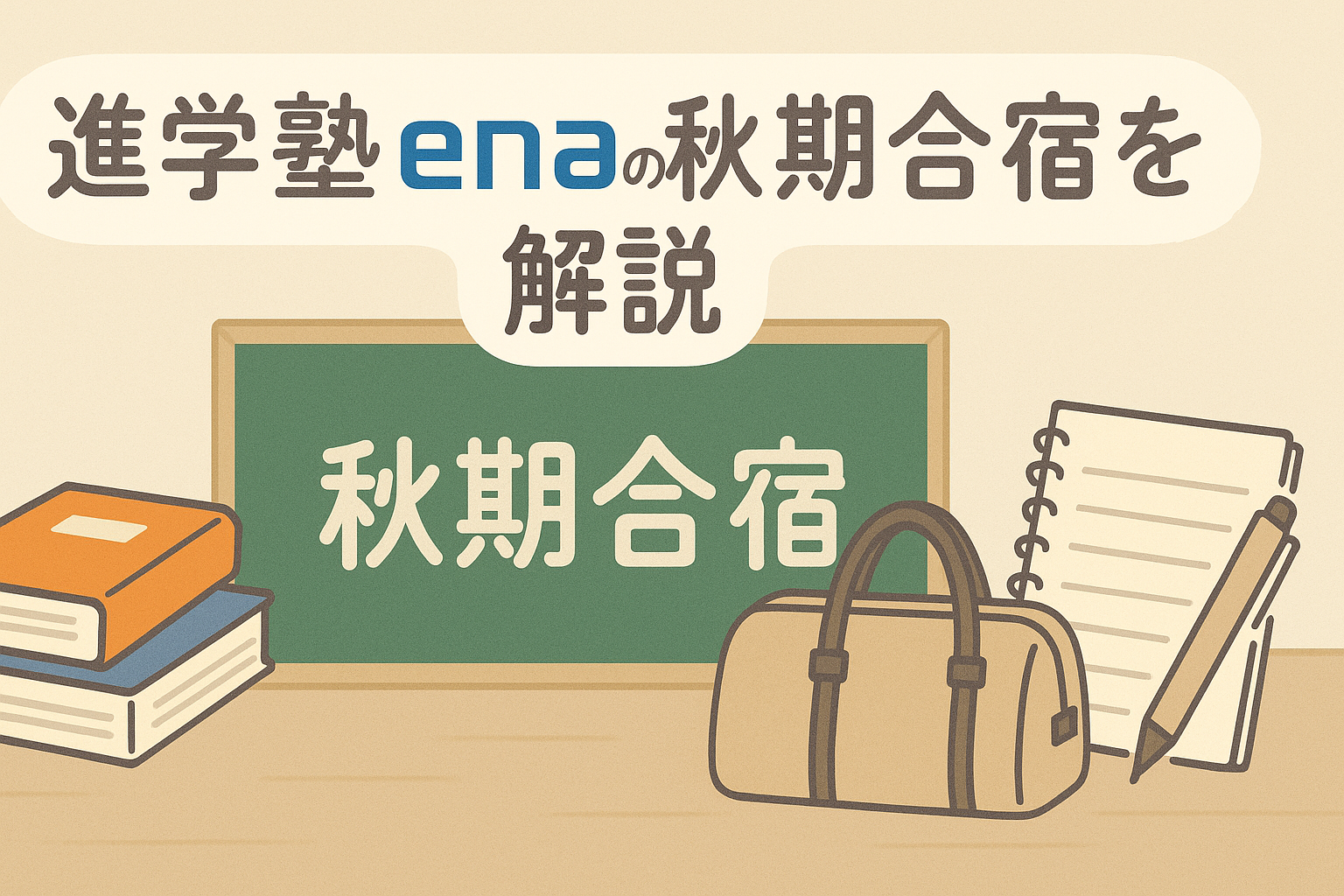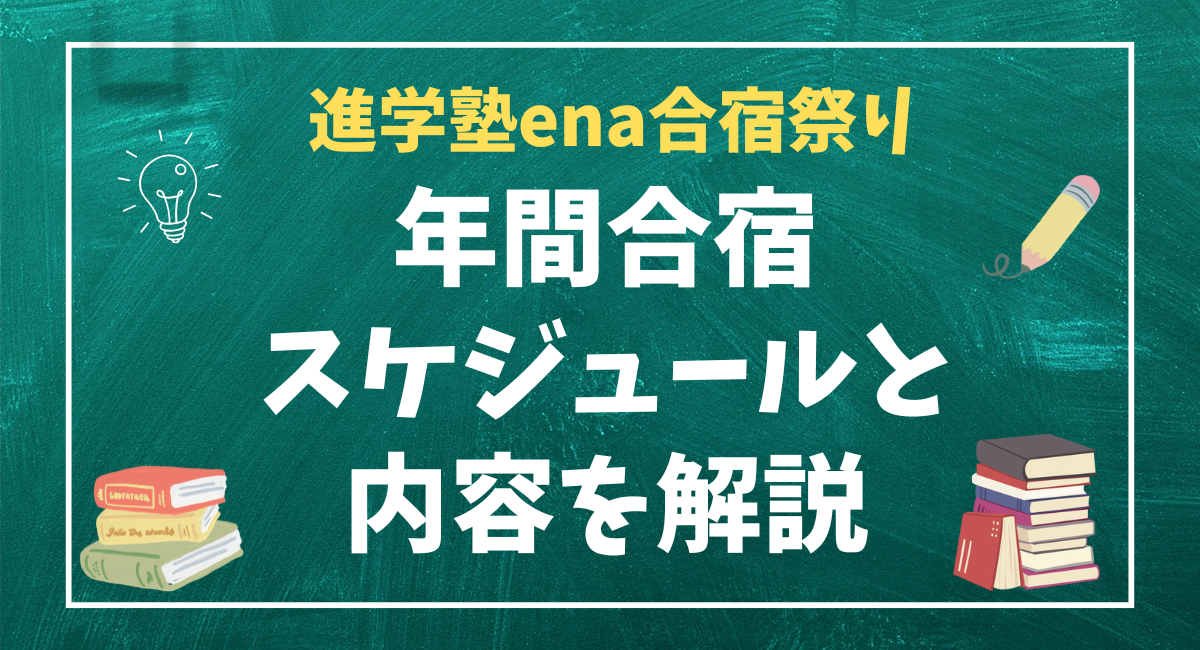はじめての中学校選び

塾に入るとまず「志望校はどちらですか?」と聞かれます。
うちの場合、小2冬に中学受験へのチャレンジを考えはじめ、それに向けてまずは学習習慣をつけることを目的に入塾したこともあり、その当時志望校なんてサッパリ決まってませんでした。ただ塾の先生からは「小4くらいには志望校が決まっている必要がある」と言われ、小3から志望校選びを始めました。
志望校を決めるキッカケづくり
志望校を選ぶと言っても親が志望校を決めている場合(我が家は代々御三家中学だ!等)を除き、小3の時点で自発的に「この学校に行きたい」と考えている子どもは限りなくゼロだと思います。それこそ、そう思うキッカケが必要です。
これから長い中学受験への学習が始まるわけで子どもに自ら志望校を決めさせた方が今後の学習へのモチベーションが維持しやすいのではないかと考え、うちでは子どもに志望校を選ばせるためのキッカケづくりを行いました。
具体的にどういったキッカケづくりができるかを考えた結果、現時点で実施できたことは「学校説明会・学園祭に行く」「中学校の最寄り駅まで出かけてみる」の2点(ごく普通なこと)でした。
キッカケづくり1:学校説明会・学園祭に行く
王道なのは学校説明会や学園祭に行き、学校の雰囲気をつかむということです。
でも、実際は学校説明会へ参加できるのは小学5年生以上とか保護者のみ等の参加制限をしているところが多く、低学年のうちから参加できる説明会が意外と少ないです。また参加できる場合であっても学校説明会の場合、当日の在校生数が少ない(説明会要員として選抜された子だけ参加してる)ので本当の学校の雰囲気がわかりにくいという面もあります。
一方、学園祭は在校生全員が基本的に参加しており学校の雰囲気がわかりやすいイベントです。ネックは1年に1度しか開催されてないことが多いため一般参加枠が限られている(抽選の場合あり)のと、当日会場は非常に混雑しているため子どもが十分に在校生と会話できなかったり、混雑具合に疲れてしまい学校そのものにネガティブな印象を受けることがあるということです。
キッカケづくり2:中学校の最寄り駅まで出かけてみる
電車通学になることがほとんどのため、その通学経路や時間というのは大事な要素です。
まず電車の混雑具合。中学校見学をしようとしても土日の電車に乗ることがほとんどだと思います。できれば平日の通学時間帯の電車を経験しておくことは大事だと思います。
次に通学経路。乗り換えの大変さや通学にかかる時間。これもたまに経験する程度だと大丈夫だと感じることが多いですが毎日と考えたときにどうか、という感覚を持つのが大事です。
最後に学校の立地。場所によっては繁華街の近くにある中学校もあります。一方のどかな落ち着いた雰囲気の場所にある中学校もあります。どっちが本人にあうか、というのは見極めておいた方がよいと思います。
子どもが志望校を選ぶ基準
うちの場合、以下にフォーカスして志望校の大枠を決めていきました。
(子どもの視点)
- 入りたいクラブがあるか
- 通学が楽しいと思えるか
- 近くの公立中に行きたいと思うか
入りたいクラブがあるかは「学校説明会・学園祭」で見定めていきました。また「最寄り駅探索」で通学は子どもにとって楽しいか(ひとりで通い続けられそうか)を確認していきました。
もう1つ大事なのは近くの公立中に行きたいと思うかです。もし子どもが近くの公立中に行きたい(公立中でも良い)と思っている場合、この先の受験勉強のモチベーション維持にも影響してきます。例えば行きたい都立中が1校だけあったとして、それ以外は特にピンとこず都立中がダメだったら公立中でも良いと思うケースです。受験勉強を始めると公立に行くのがもったいないと思うのが親心ですが、公立中でも良いと子どもが思う場合、無理に複数の中学受験をする必要はなくなってきます。こうなってくると非常に難しい選択を迫られることになるので、子どもが公立中に対してどのような印象を持っているか、を確認しておくのは大事な点になります。うちの場合、幸い(?)公立中にポジティブな印象がなかったため、わかりやすく中学受験にチャレンジする方向に意識が向きました。
小学4年生の終わりまでに絞り込み
うちの場合、小3から志望校を選びを始めた結果、ある程度の方向性が固まりました。(子どもが入りたいクラブがある都立中と私立中の数校)
ここからもう1歩、まだ見学できてない学校にも足を運び、最終的な志望校を絞り込み、確定していこうと思っています。
志望校選びを始めた頃は、子どもの意思で行きたい志望校なんて決められないんじゃないか、と思っていました。ですが、いま振り返ると「決められないんじゃないかと決めつけ、何も始めなかったら永遠に決まらない」し「考えはじめると次第に決まってくる」ということです。
今回の経験から強く思ったのは、子どもの可能性の芽を親の勝手な判断で潰さないようにしないといけない、ということです。時間はかかるかもしれませんが、一生を左右する大事な選択。子どもが納得できるように引き続きサポートを続けていきたいと思います。ご参考まで。