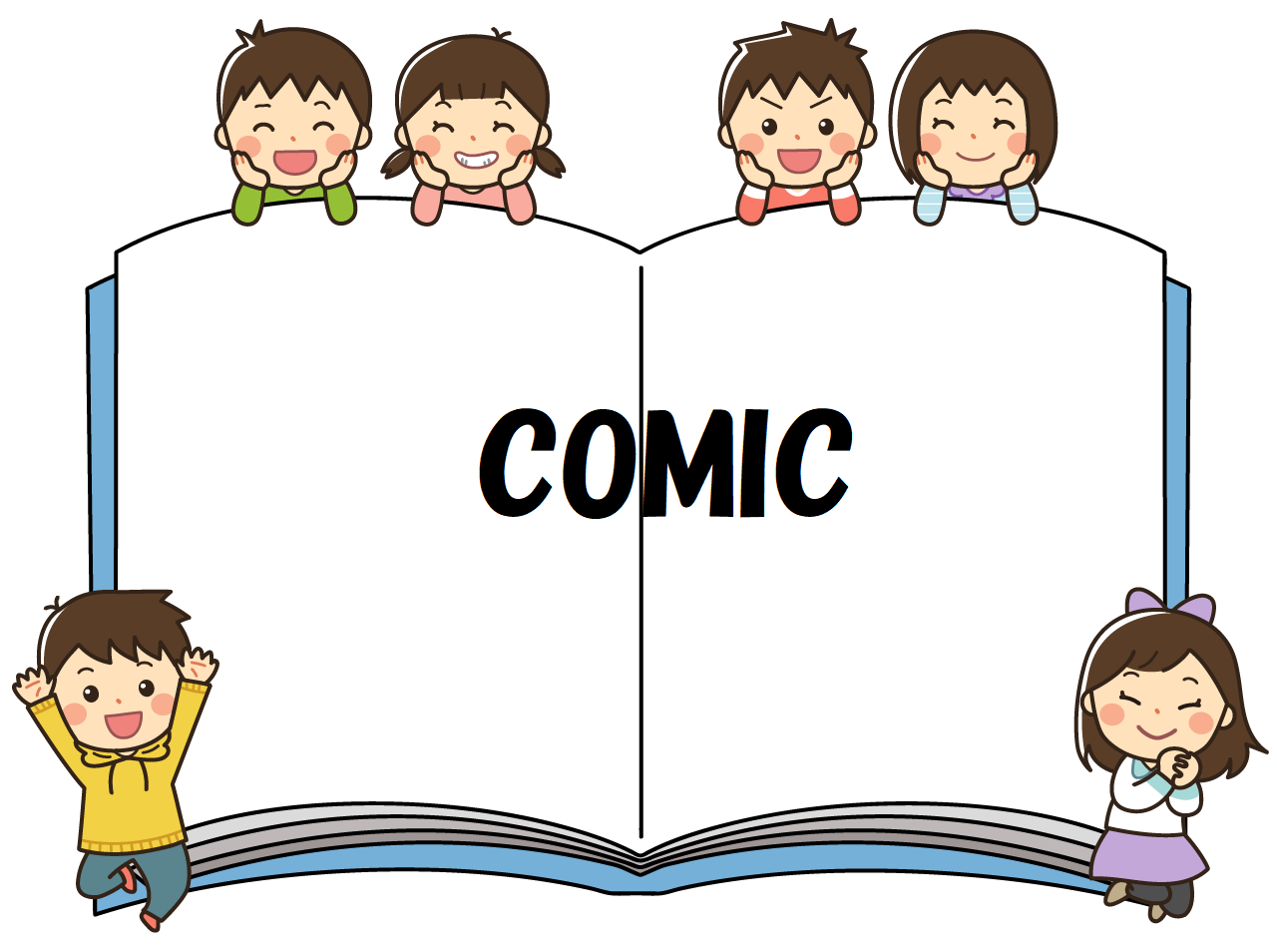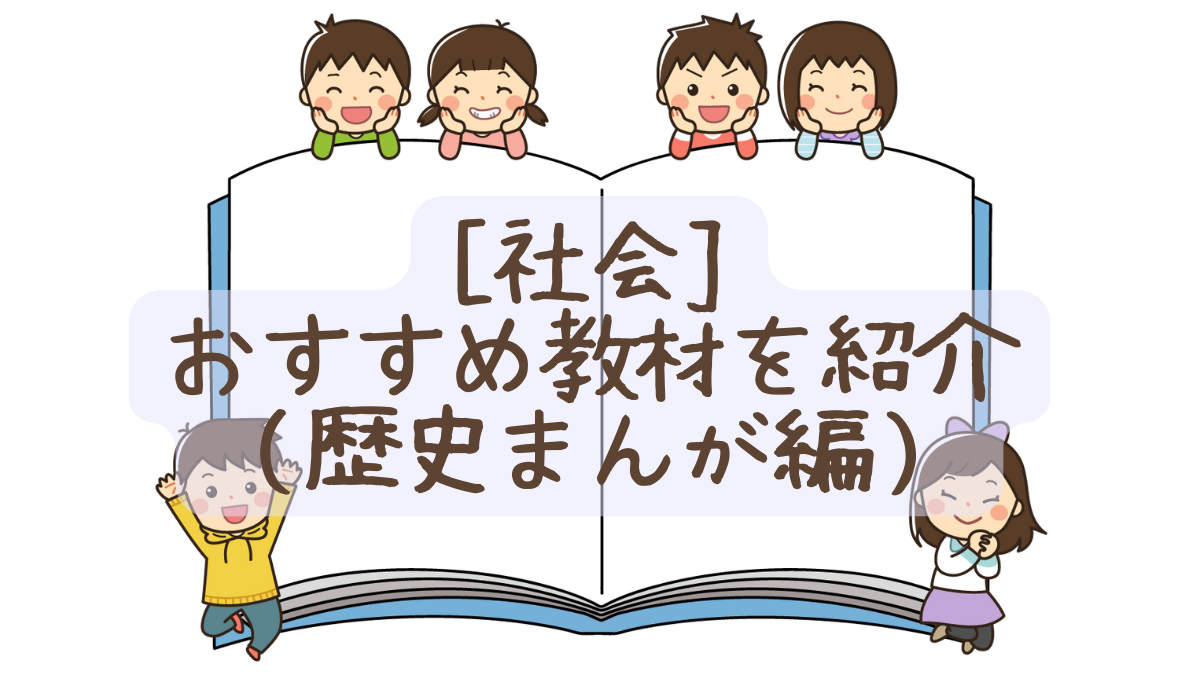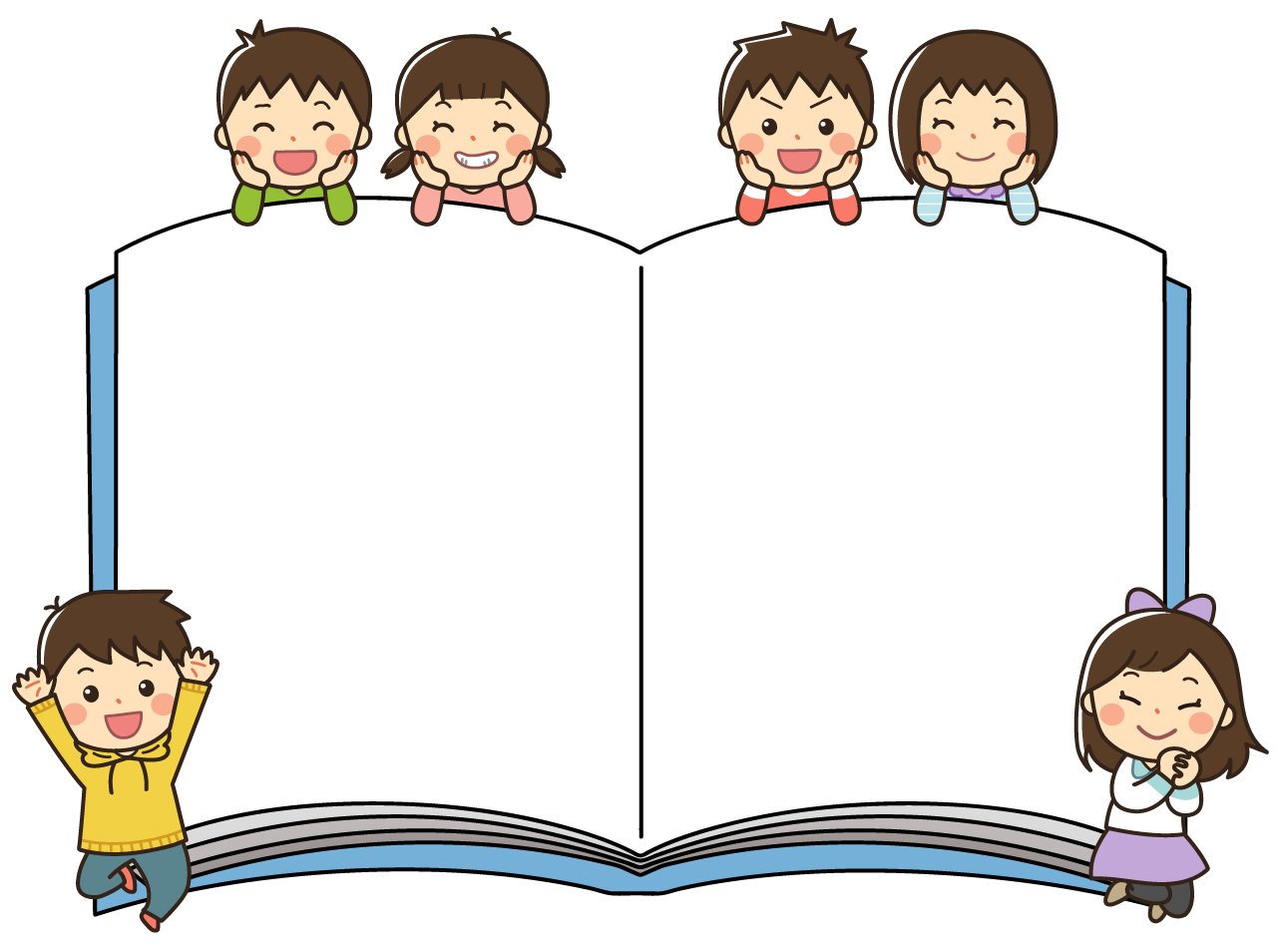歴史の学びが都立中高一貫校の受験に効く理由 〜織田信長から学ぶこと〜

都立中高一貫校の受験では「ただ知っている」だけでは合格できません。複数の資料を読み解き、自分の考えをまとめて表現する力が求められます。実はその力、歴史の勉強からしっかりと身につけることができます。
今回は戦国時代の英雄・織田信長を題材に歴史がどのように受験に役立つかを考えていきます。信長の功績をただ賛美し記憶するのではなく「なぜそれを行ったのか」「本当に正しかったのか」という視点から深掘りすることが大事です。これこそが、都立中高一貫校が求める力です。
うちでは、こちら↓の本を子どもと一緒に読んだあと、後述する観点について一緒に考えてみました。
1. 長文を読み解く力がつく
信長には「室町幕府を滅ぼした」「本能寺で家臣に裏切られ人生を終えた」という数々のエピソードがあります。
その歴史上のイベントに目が行きがちですが「なぜ室町幕府を滅ぼしたのか?」「なぜ本能寺で家臣に裏切られたのか?」といった問いを持つことが重要です。
なぜ室町幕府を滅ぼしたのか?
室町幕府は全国をまとめる力を失い、戦乱の時代が続いていました。信長はその状況を変えるため古い体制に見切りをつけ、実力で新しい支配を目指しました。これはただの反抗ではなく乱世を終わらせるための判断でした。
なぜ本能寺で裏切られたのか?
家臣・明智光秀による本能寺の変は、信長の独裁的な行動への反発や、家臣との信頼関係の崩壊が背景にあります。つまり、どれほどのリーダーであっても、周囲を無視すれば反発を招くという教訓でもあります。
これらを読み解くには、歴史的背景・人物の心理・社会情勢を総合的に考える力が必要です。これはまさに受験の長文読解と同じ「文脈を読む力」です。
2. 因果関係を考える力が育つ
歴史を学ぶうえで大切なのは「なにが起きたか」ではなく「なぜそれが起きたのか」「その後どうなったのか」を考えることです。
信長には「楽市楽座を開いた」「戦に鉄砲を活用した」というエピソードもありますが、こちらもその表面的なエピソードだけではなく、その裏側までを考えることが大事です。
なぜ楽市楽座や鉄砲の活用を進めたのか?
楽市楽座では商人の営業を自由化し経済を活性化。鉄砲の活用では伝統的な戦い方を変えて効率的な戦術を導入しました。すべては、効率よく勢力を広げ、力を安定させるためでした。
その結果、どう社会が変わったのか?
信長が勢力を拡大した地域では経済が発展し城下町が生まれ、封建的な身分制度が揺らぎ始めました。つまり、信長の革新は日本が近代国家へと進む土台をつくりました。
このように、歴史の因果関係を追うことで受験でよく出る「なぜ?どうして?」に強くなれます。
3. 資料を読み取るスキルが上がる
歴史の学習では、年表・地図・人物関係図など多くの資料を扱います。
今回紹介した学習まんがにも中表紙に地図や年表が載っています。本編だけでなく、こういった付帯資料も一緒に眺めてみることで相乗効果が得られます。
年表から読み取れること
年表からは、信長の戦略や歴史上の転換点が読み取れます。
【勢力拡大・支配安定の時期】
1551年:織田信長が家督を継ぐ(尾張国)
1567年:美濃を平定し、稲葉山城を岐阜城と改名して本拠地とする
1568年:足利義昭を奉じて上洛、室町幕府に影響力を持ち始める
1573年:足利義昭を京都から追放し、室町幕府を事実上滅ぼす
1575年:長篠の戦いで鉄砲を用いて武田軍に勝利、支配の安定期に入る
【反対勢力が増え始め内外でも緊張が高まった時期】
1576年:安土城の築城開始、政権の中心を安土へ移す
1582年:明智光秀に裏切られ、本能寺の変で自害
地図から読み取れること
地図を見ることで、なぜ岐阜城を拠点にしたか、なぜ京都を目指したかを理解する助けになります。
- 岐阜城は木曽川と山地に囲まれ、防衛に優れながらも、東西への交通の要所に位置しており、軍事・経済両面で拠点として最適だった。
- 京都は当時の政治・宗教の中心地。信長はここを支配下におくことで、天下統一への正当性と影響力を高めようとした。
家系図や人物相関図から読み取れること
人物相関図からは、家臣や同盟者との力関係が見えてきます。
- 信長は婚姻関係(斎藤道三の娘との結婚など)や同盟(徳川家康との清洲同盟など)で着実に味方を増やした。
- しかし、武田家との対立、浅井・朝倉との同盟破棄、そして明智光秀との関係悪化など、忠誠と裏切りが交錯する。
- 組織内での緊張が高まり、家臣団の中でも不満が蓄積され、やがて本能寺の変という結果につながる。
これらはすべて、適性検査Ⅰ・Ⅱで頻出の「資料読み取り問題」そのものです。歴史を通じて、図表を読み取る力が身につきます。
4. 表現する力、自分の意見を持つ力が育つ
歴史はただ「覚える」だけでなく、そこから「自分の意見」を持つことが、最も重要です。
例えば「信長が現代にいたらどんな改革をしたか」「信長と家康、どちらがより優れたリーダーか」といった問いに、自分なりの答えを出すこと。それはそのまま、作文型問題(適性検査Ⅲ)で必要なスキルです。
そして最後に、もう一歩踏み込みたい問いがあります。
信長は本当に“理想のリーダー”だったのか?
信長は戦国を終わらせるために戦い、古い秩序を壊し社会を前に進めました。けれど同時に多くの人を犠牲にし、武力や恐怖で支配した側面も否定できません。
今の国際社会では「人を傷つけてまで目標を達成していいのか」という価値観が問われます。その視点で見ると、信長のやり方は再評価されるべき部分が多くあります。
本当の学びとは、「問い」を持つこと
信長の行動から私たちが本当に学ぶべきなのは、「やり方」よりも「限界」です。
- いかに革新的でも、対話や信頼を欠けばひずみが生まれる
- 力で支配しても、それは長続きしない
- 社会を変えるには、理念と人の心の両方が必要
こうした視点をもつことが、未来の社会を担う子どもたちに必要な力です。そして、それはまさに都立中高一貫校が重視する「思考力・表現力・社会性」に直結します。
おわりに:歴史は正解を教えない。でも、問いをくれる
信長を学ぶことで得られるのは、英雄伝でも年号の暗記でもありません。
それは「このやり方でいいのか?」「もっと良い方法があったのではないか?」という“問い”を持つこと。そして、自分の答えを模索すること。
都立中高一貫校の受験が求めているのは、まさにその力です。
だからこそ、歴史を学ぶことは、単なる知識の積み上げではなく、未来をつくるための思考トレーニングになります。
中学受験の準備では、計算問題や知識を問う問題を大量に解くことが学習の王道です。対して歴史の深堀は一見遠回りのように感じることがあるかと思いますが、最終的な総合力向上につながるため、うちでは引き続き、歴史の深堀学習をしていきたいと思っています。